
|

|

|



|

|

|

|



|

|

|

|



|

|

|

|



|

|

|

|



|


|

|

アルツハイマー病は、進行性の認知症を主症状とする脳の疾患です。国内外の医学界で遺伝子の異変を主原因と考えて、その発症機序解明の研究が行われていますが、アルツハイマー病の発症の機構は次のように考えられています。

|

|

|

|



|


|

|

最近のアルツハイマー病関連国際会議の内容を以下に示します。
|
●
|
「第5回アルツハイマー病及び関連疾患に関する国際会議」:1996年7月大阪で開催。42か国、1300人が集まった国際会議においても演題809件の大多数が「アポリポ蛋白E」及びアルツハイマー病の遺伝子に関する研究報告でした。
|
|
●
|
「第11回精神研国際シンポジウム」:1997年3月東京で開催。講演の内容は、アポリポ蛋白E及びプレセニリン等の遺伝子要因の研究報告でした。
|
|
●
|
「第6回国際アルツハイマー病会議」:1998年7月アムステルダムで開催されました。アルツハイマー病に関して、現在実質上最も確立された国際会議であり、1300件以上の研究報告がなされました。その中では遺伝子を中心にした考え方が定着して来ており、アルミニウムに関連したものは1300演題中、日本からの一件を含む数件のみでした。アルツハイマー病に対する決定的治療法の開発はもうしばらく時間がかかるようです。アルツハイマー病の発症メカニズムなど病態が解明されるにつれ、それを抑制する薬の研究及び予防する薬の研究も進められつつありますが、現時点では研究段階であり、実用化されているものはごくわずかです。
|
|

|

|

|



|


|

|

認知症とアルツハイマー病と混同される人がいます。一口に認知症と言っても大きく次のように分類されます。
|
脳血管型認知症
|
脳血管の病変が原因で、血管が閉塞し生じる認知症
|
|
アルツハイマー型認知症(老年性)
|
遅発性、緩進行性、孤発性の認知症
|
|
アルツハイマー病(家族性)
|
若年発症、進行速い、遺伝性の認知症
|
|
混合型認知症
|
中毒性要因、低酸素性、甲状腺機能障害等による認知症
|
|

|

|

|



|


|

|

記憶や判断力など知的機能の著しい低下が中心的な症状です。
認知症の進行のステージとして、健忘期(記憶障害)→ 混乱期(失語、徘徊、精神混乱)→ 認知症期(高度の認知障害)があり、全経過は3年から10年以上と大きな差があります。全ての患者が認知症期まで至るとは限りませんし、健忘期に留まることが長い人もいると思われます。
[補足説明]
アルツハイマー病が世の中に認識された時期:最初のアルツハイマー病の報告は、1906年ドイツの精神医学者Alois Alzheimer によって、51歳で発病した女性の認知症患者についてなされた。
|
(1)
|
この病気が発見されて一世紀近く経とうとしていますが、最近まで原因不明であり、治療法が確立されていません。この10年間で病理の一部が解明されてきました。
|
|
(2)
|
Alzheimer 博士が発見したこの病理の特徴は、脳の委縮、神経細胞の著しい減少、及び、「老人斑」 と「神経原線維変化」が広範に認められることです。
|
|
(3)
|
ADの病理及び分子生物学研究はこれまで、βアミロイドやタウの形成・沈着等の異常構造物及び蓄積物質を中心として行われてきました。これらが解明されると、その代謝過程の操作によりアルツハイマー病の治療が可能となることが期待されます。
|
|
(4)
|
近年の分子遺伝学の進歩により次の4種の遺伝子が原因遺伝子として発見されています。
・21番染色体に存在する「アミロイド前駆体蛋白(APP)」遺伝子
・14番及び1番染色体に連鎖する「プレセニリン-1及び-2」遺伝子
・19番染色体に存在する「アポリポ蛋白E」遺伝子
|
|
(5)
|
アルツハイマー病は遺伝子因子と環境因子が組み合わさった複雑な病気であり、老年期認知症の双壁である血管性認知症との鑑別が重要です。βアミロイドとタウの蓄積をコントロールする治療法は今後の課題です。
|
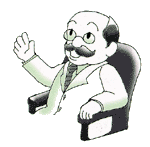
アルツハイマー病発症の要因
前記のようにアルツハイマー病は、遺伝子要因と他の要因が複合した多因子型の病気と言われており、次のような代表的因子があげられます。
|
●
|
遺伝子要因(アミロイド前駆体蛋白、βアミロイド、
タウ蛋白、アポリポ蛋白E、プレセニリン)
|
|
●
|
環境要因(加齢、性別、頭部外傷、喫煙、教育)
|

|
アミロイド前駆体蛋白(APP)−
|
βアミロイド蛋白の元になる蛋白質。
|
|
βアミロイド−
|
APPから切り出されて生成するもので、老人斑アミロイドの主要構成成分。
|
|
アミロイド−
|
蛋白質が細胞外で重合し、線維が密に集合したもの。
|
|
アポリポ蛋白E−
|
血清リポ蛋白の代謝などに関与する蛋白である。生成は肝臓が最も多く、次に脳があげられる。
|
|
プレセニリン−
|
早発性家族性アルツハイマー病の原因遺伝子として1995年に同定された。第14染色体上にあるプレセニリン-1遺伝子(PS1)と第1染色体上にあるプレセニリン-2遺伝子(PS2)があり、PS1には現在までに30種近い点突然変異が見出されている。
|
|
老人斑−
|
アルツハイマー脳、老人脳に出現する斑状の病理変化。細胞外に蓄積したβアミロイド、反応性グリア細胞。
|
|
神経原線維変化−
|
神経細胞内の線維蓄積物でねじれ細管を含む。主要構成成分は微小管結合蛋白タウである。アルツハイマー病を特徴づけるものであるが、他の中枢神経疾患でもみられる。
|
|

|

|