1.老化とアルツハイマー病:オーバービュー
| |
国立長寿医療センター研究所長 田平 武 |
| |
アルツハイマー病の頻度は年齢と共に幾何級数的に増加して行きます。実際65歳位の人のアルツハイマー病の頻度は2%位ですが、5年歳をとるごとにその頻度は倍々と増え、85歳位になると3人に1人がアルツハイマー病という状態になります。それでは100歳になっても増え続けるかというとそうではなく、85歳を過ぎるとアルツハイマー病の頻度はむしろ減少してきます。従ってアルツハイマー病は脳の究極の老化ではなく、加齢を最大の危険因子とする脳の病気である、と言えます。アルツハイマー病が病気であるなら、原因をつきとめれば予防・治療できる筈であり、それは老化を制御するよりはるかにやさしいと考えられます。多くの研究の結果、アルツハイマー病はアミロイドベータ蛋白がその発症に重要な係わりを有していることが分かり、アミロイドベータ蛋白を作らなくしたり除去したりする方法が開発され、実用化に向けて着々と研究が進んでいる状況です。秋山先生にはその病因についてアルミニウムの実験結果も含めてお話頂きます。
こうしてアルツハイマー病が解決すると後に残るのはその他の病気による認知症と脳の老化そのものによる認知症が大きな問題として浮かび上がってきます。とくに90歳以降の超高齢者の認知症はまだ十分実態も分からない状態です。その中から山田先生は神経原線維変化優位型認知症というものを見つけられました。これは脳の老化とも考えられ、超高齢者の認知症の主たる原因となっているようです。
こうなると老化を理解し、これを制御する方法を考えたくなります。丸山先生には老化のメカニズムがどこまで分かったか、科学的アンチエイジング法というのはあるのかについてお話頂きます。このフォーラムによってアルツハイマー病や脳の老化について皆様の理解が深まり、いつまでも私達の脳を健康に保つにはどうすればよいかということを考える機会が与えられることを期待します。 |
|
|
2.アルツハイマー病の病因
| |
東京都精神医学総合研究所参事研究員 秋山治彦 |
| |
1911年にドイツのアルツハイマー博士が、進行性の認知症で亡くなった患者さんの脳を顕微鏡で観察した結果を論文にまとめました。そこで示されたアルツハイマー病の特徴は、大脳の萎縮と神経細胞の減少、老人斑と呼ばれるシミのようなものの多発、神経細胞の中に出現する繊維状の塊(神経原線維変化と呼ばれます)、の3つでした。それから約70年後に老人斑のシミがアミロイドβたんぱく質(Aβ)と呼ばれる物質の異常な蓄積であることがわかりました。ところで、アルツハイマー病の数%は家族性に発病します。残りの大部分のアルツハイマー病の患者さんでは明らかな遺伝は認められません。家族性アルツハイマー病を引き起こす遺伝子は実はひとつではなく、家系により異なる遺伝子の異常によって、同じアルツハイマー病という病気が起こります。今日までに3つの遺伝子が発見されていますが、それらの遺伝子に異常がない家族性アルツハイマー病の家系がまだありますので、将来、アルツハイマー病の遺伝子の種類はもっと増えると思います。その3つの遺伝子のひとつが、実はAβのもとになるたんぱく質(Aβ前駆体たんぱく質)です。このAβ前駆体たんぱく質の遺伝子異常は、脳へのAβの蓄積を増加させる作用があることがわかっています。また、別のアルツハイマー病遺伝子――プレセニリンと呼ばれています――の異常も、やはり脳へのAβの蓄積を増加させます。そこで、これらの遺伝子異常を人工的に組み込んだマウスが作られ、マウスの脳にAβ蓄積を起こすことができるようになりました。一方、神経原線維変化はタウと呼ばれるたんぱく質の異常な蓄積によってできます。このタウに遺伝子異常があるとタウが脳に蓄積しやすくなりますが、この遺伝子異常はヒトではアルツハイマー病とは違う病気を引き起こします。ただ、タウの遺伝子異常を持ったマウスに、さらにAβ蓄積を起こす遺伝子異常を組み込むと、Aβが蓄積している場所に神経原線維変化ができるようになります。
これらの研究から推測されることは、アルツハイマー病の原因はたくさんあるけれど、個々の原因にかかわりなく、Aβの脳への蓄積の有無がアルツハイマー病になるかならないかを決めるカギである、ということです(この考え方をAβ仮説と呼んでいます)。現在、このAβ仮説は非常に多くの研究者の支持を得ていて、Aβの脳への蓄積を減らす、あるいは消失させるための薬剤や治療法が急ピッチで開発されています。そのような中で、アルツハイマー病研究の大きなテーマとして浮かび上がってきたのが、一つはAβの脳への蓄積を検出してアルツハイマー病を早期に、すなわち認知症が始まる前に診断できるようにすることです。これについては、本邦でもこの4月からJ-ADNIと呼ばれる数年がかりの大規模研究が開始されました。もう一つは、やはりAβの脳への蓄積ということをカギとして、アルツハイマー病になりやすい要因を見つけること、そして、それが本当にアルツハイマー病の危険因子であるかどうかを、厳密な疫学や動物実験によって確かめることだろうと思います。たとえば、以前、アルミニウムの摂取がアルツハイマー病の原因になるかもしれないと言われたことがあります。しかし、疫学調査の結果はそれを行った研究者によってまちまちで一貫していませんでした。そこで、私たちはAβが脳に蓄積する遺伝子操作マウスに、一生の半分以上の長い期間、大量のアルミニウムを飲み水に混ぜて経口摂取させ、脳へのAβ蓄積が増加するかどうかを調べてみました。結論だけ申しますと、アルミニウムを過剰に摂取しても――実際には体重あたりヒトで許容されている量の100倍を投与しました――脳へのAβ蓄積は増加しませんでした。さらに、タウとの二重遺伝子操作マウスを用いて同じ実験をしましたが、Aβ蓄積に伴う神経原線維変化の増加もアルミニウム投与の影響を受けませんでした。
最近、私たちのアルミニウム投与の実験と同じように、マウス脳へのAβ蓄積を指標に、様々な危険因子が調べられています。たとえば、高コレステロール血症をはじめとする動脈硬化を促進するいくつかの因子がAβ蓄積も増加させる、という結果が知られています。また逆に、Aβ蓄積を起こしにくくする要因も報告されています。広いケージの中にトンネルやおもちゃをいくつも設置してあげて、毎日たくさん運動をして一生を過ごしたマウスは、通常の狭いケージの中で運動不足のまま過ごしたマウスよりもAβ蓄積が少ないと言われています。もちろん、ヒトのアルツハイマー病ではどうか、ということはこれからさらに検討していかなくてはなりませんが、高血圧や動脈硬化、糖尿病などの予防も兼ねて日常生活に運動を取り入れるのは、いろいろなメリットがありそうです。近い将来、高齢になってもアルツハイマー病になりにくく、仮になってしまっても、認知症が出現する前に検査で発見して進行を止める治療をすることができる、そんな時代が来るのではないかと期待しています。 |
|
|
3.老化に関連しておこる非アルツハイマー型認知症
| |
金沢大学大学院医学系研究科神経内科教授 山田正仁 |
| |
(1) 認知症をおこす病気にはいろいろある
認知症を有する人の割合は加齢と共に増加し、85歳以上では30%近くの人にみられる。
認知症をおこす疾患はいろいろある(表)。表の分類によると、【1】変性型、【2】脳血管性、【3】その他に大別され、さらに変性型はアルツハイマー型(アルツハイマー病)と非アルツハイマー型に分けられる。それらの頻度では、わが国では従来、アルツハイマー病よりも脳血管性認知症の頻度が高いと考えられていたが、近年ではそれが逆転し、欧米同様に認知症患者の過半数はアルツハイマー病と考えられている。さらに最近では、非アルツハイマー型変性型認知症、特にレビー小体型認知症がかなりの頻度でみられることが判明してきている。すなわち、非アルツハイマー型変性型認知症は、脳血管性認知症と共に、アルツハイマー病に次ぐ位置を占めている。また、脳血管障害(脳梗塞など)による脳血管性認知症はもちろん、非アルツハイマー型変性型認知症に属する疾患も加齢との関係が深い。本講演では、最近注目されている非アルツハイマー型変性型認知症に焦点を当て紹介する。
表. 認知症の原因疾患
【1】変性型認知症
 |
a. |
アルツハイマー型(アルツハイマー病) |
| |
b. |
非アルツハイマー型(レビー小体型認知症、神経原線維変化型老年認知症、嗜銀顆粒性認知症、前頭側頭型認知症(ピック病など)ほか) |
【2】脳血管性認知症
【3】その他の原因疾患
 |
a. |
内科的疾患:ビタミンB1欠乏症、甲状腺機能低下症、アルコール、神経梅毒、脳炎など |
| |
b. |
脳外科的疾患:慢性硬膜下血腫、正常圧水頭症など |
|
|
(2) 非アルツハイマー型変性型認知症
1. レビー小体型認知症 : 認知症の10数%〜20%を占めるといわれている。α-シヌクレインというタンパク質が蓄積したレビー小体という異常構造物が多数の神経細胞に非常に広範囲に出現し、認知症、幻視、抑うつなどの精神症状、パーキンソン症状などを呈する。レビー小体が脳幹部にだけ出現する場合は、パーキンソン病に該当する。MIBG心筋シンチグラフィーという心臓交感神経の検査が本疾患とアルツハイマー病ほかの認知症性疾患との鑑別に有用である。認知症や精神症状の治療にはアルツハイマー病と同様に塩酸ドネペジルが有効である(ただし保険適応未承認)。
2. 神経原線維変化型老年認知症 : 本疾患(辺縁系神経原線維変化認知症、神経原線維変化優位型認知症などともよばれる)は、アルツハイマー病と同様に海馬領域を中心に多量の神経原線維変化(異常リン酸化タウタンパクの蓄積)が存在するが、アルツハイマー病とは異なり脳全体で老人斑 (アミロイドβタンパク沈着)をほとんど欠くという特徴を有する。高齢で発症し記憶障害を主体として緩徐な進行を示す。本症は認知症高齢者の約5%にみられ、90歳以上では20%に達する。
3. 嗜銀顆粒性認知症 : 本疾患は神経細胞の突起における嗜銀性顆粒(異常リン酸化タウタンパクの蓄積からなる)の出現を特色とする。嗜銀性顆粒は加齢と共に増加し、側頭葉内側部から辺縁系に拡大し、認知障害(記憶障害あるいは感情・人格面での変化)を呈する。本疾患は全認知症患者の約5%を占めるとの報告がある。
4. 前頭側頭型認知症 : 前頭側頭型認知症は人格変化や行動異常に特徴づけられる症候群であり、大脳の前方部(前頭葉と側頭葉)に限局した萎縮を示し、後方優位の異常を示すアルツハイマー病と対比される。前頭側頭型認知症の原因にはさまざまな疾患が含まれる。異常リン酸化タウタンパクが蓄積したピック球が神経細胞内に出現するピック病は代表的な疾患である。
(3) 今後の課題
ここにあげたレビー小体型認知症、神経原線維変化型老年認知症、嗜銀顆粒性認知症は、しばしばアルツハイマー病と誤診されてきた。これらの中では、レビー小体型認知症は比較的研究が進んでいるが、神経原線維変化型老年認知症や嗜銀顆粒性認知症とアルツハイマー病との鑑別診断法は確立されていない。アルツハイマー病の治療法と共に早期診断法の開発研究が進んでいるが、アルツハイマー病の診断精度を上げるためには、アルツハイマー病との鑑別が問題となる非アルツハイマー型変性型認知症の早期診断法を確立することが必要である。
|
|
|
4.老化のメカニズムと科学的アンチエイジング
| |
東京都老人総合研究所副所長 丸山直記 |
| |
青春期を過ぎて更に年齢を重ねると私たちは病気ではないが様々な身体的不具合を日々経験するようになります。そして不具合の生じる部位や程度は個々人により全く異なっています。この様な有様は老化の特徴と言えるでしょう。すなわち加齢という時間経過は老化という必ずしも病気ではない個人差の大きな身体機能の低下をもたらします。この老化現象の背後に存在する最も重要な要因はなんでしょうか? この解明はアンチエイジングに必要です。老化の原因として様々な仮説が提唱されて、消えて行きました。その中でも1956年に米国のデナム・ハーマン博士により発表され、現在も多くの研究者に支持されている学説が「フリーラジカル説」です。私たちは自動車と同じように生体内で酸素を燃やしエネルギーを得ています。その過程で発生する有害因子(フリーラジカル)により生体成分が酸化、言い換えると「錆び」てしまいます。このような生体に及ぼす影響を「酸化ストレス」と呼んでいますが、この「酸化ストレス」を抑制することはアンチエイジングの重要な課題の一つとなっています。
老化は個人差が大きいことが特徴ですが、その程度を「測る」ことができれば老化抑制に役立つことでしょう。私たちはこの目的を達成するための老化研究の過程で加齢に伴い減少するSMP30という蛋白質を発見しました。発見当初、その働きは全く謎でした。それでもオウム事件で有名になったサリンを分解したり、ホタルが光ることに役立っていることなどが証明されましたが、真の働きは不明でした。最近、私たちはSMP30が原始的な細菌が持つグルコノラクトネースという酵素と同一のものであることを解明しました。この酵素はネズミにおいてはビタミンCの合成に関わっていることも明らかになりました。私たちはSMP30が欠損した実験動物を用いてビタミンCの欠乏が老化に与える影響を解析しました。以前からビタミンCは老化抑制作用を持つとされていましたが、実は科学的な研究報告はなされていませんでした。私たちはビタミンCの欠乏が体内の「酸化ストレス」を亢進させ老年病に罹患しやすい状態にさせることを証明してきました。例えばビタミンC欠乏動物の脳や肺では酸化ストレスが増加します。この事実はビタミンC欠乏によりアルツハイマー病や、喫煙による慢性閉塞性呼吸器病(COPD)が発症しやすくなることが考えられます。しかし動物実験で明らかにされたことを検証も無く人間に当てはめることは危険なことです。例えばビタミンCの過剰投与が時に病態を悪化させる可能性があるという科学的な報告もあります。私たちの健康維持に重要と思われる情報を検証も無く、単純に信ずることは危険なことです。冷静な目を持ち科学的なアンチエイジングの方法を開発・育成することが必要です。 |
|
|
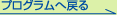 |