| ■数値の違いは測定法が原因か |
この表【表3】は、アルミニウムが人間の体内にどのくらい存在するのかについて、以前に学術誌に掲載された報告例である。これを見て気がつくのは、報告者によって値が非常にずれるということである。これは測定方法が悪いのかもしれない。たとえば平均値だけを見てもかなり違う。
私たちが尿中のヒ素の検査をするとき、「前2日間は魚介類を食べないでください」と言うが、そうしないと魚介類を食べて影響を受けているのか、そうでないかがまったくわからなくなるからだ。
このようなデータについては、いつごろ測定されたかという点もたいへん重要だ。クロムの測定値【図5】を見ると、正常人の血清中では、1950年には約100ppbという報告がされたのだが、1960年になると1,000ppbを超えるという報告がある。ここですでに10倍の違いがある。ところが1980年になると、正常値は0.2ppbか0.5ppbぐらいに変わる。また尿中に存在するクロムの場合は、1974年の正常値が7.1μg/day。ところが1982年になると、0.16μg/dayという報告がある。人間の側の正常値がこれほど変化するとは思えない。したがって、やはり測定法に問題があったと思われるのである。 |
【表3】生体試料中アルミニウム正常値(真鍋重夫、日本臨床、47、1989)
| 生体試料 |
正常値 |
測定法 |
報告者 |
| 体内総量 |
50〜150mg |
計算値 |
Heupke(1950) |
| |
61mg |
計算値 |
ICRP(1975) |
| |
50mg |
計算値 |
Alfrey(1980) |
| 全血液中含量 |
12.5±4μg/l |
ICPES |
Allain(1979) |
11.14±0.88mg%
(灰分重量率) |
発光分析 |
Shevaga(1973) |
| 血清(血漿)中含量 |
25〜1,460μg/l |
放射化分析 |
Beriyne(1970) |
| 42±16μg/l |
ICPES |
Schramel(1980) |
| 3.7±1.1〜49±11μg/l |
フレームレス原子吸光 |
Alfreyのまとめ(1983) |
| 6±3μg/l |
フレームレス原子吸光 |
Alfrey(1983) |
| 12.4±6.5μg/l |
フレームレス原子吸光 |
McNeil(1984) |
| 髄液含量 |
31±11μg/l |
放射化分析 |
Delaney(1980) |
| 6.8±4.5μg/l |
フレームレス原子吸光 |
Alfrey(1983) |
| 尿中含量 |
86±65μg/日 |
放射化分析 |
Recker(1977) |
| 16±8μg/日 |
原子吸光 |
Kaehney(1977) |
| 61±22μg/日 |
フレームレス原子吸光 |
Gorsky(1979) |
| 4.7±2.5μg/日 |
ICPES |
Allain(1979) |
| 13±6μg/日 |
フレームレス原始吸光 |
Alfrey(1983) |
| 胆汁中含量 |
3±1μg/l(イヌ) |
原子吸光 |
Alfrey(1983) |
|
| 【図5】血清、尿中クロム含量正常値の変遷 |
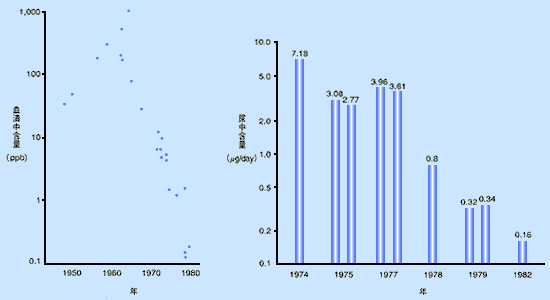 |
|
|