| ■体内での微量元素の動き |
人間が食べ物などで体内にアルミニウムを摂取すると、アルミニウムは消化管を通って一部吸収され、それを素通りしたものは便として排出される。職業的に有害物質を扱う人は、職種によって半年から1年に一度、特殊健康診断を行うが、有害物質の吸収を診断するには便ではなく尿を調べる。便と違い、尿の中には体内に一度吸収された物質が入ってくるからである【図6】。
私たちは無菌状態の中で生活しているのではないので、実際は雑菌をたくさん食べて生活している。しかし、たとえばコレラ菌を少しぐらい食べてもコレラにかかることはない。これは、健康な胃を持っている人は、胃の中で胃酸が分泌してコレラ菌など大部分の菌をやっつけて、菌が死んでしまうからだ。同様に、小腸の中には非病原性の大腸菌がたくさん存在して、これが菌をやっつける。専門家の間では、コレラ菌は一億個食べると発症するが、それ以下なら発症しないと言われている。また、よく知られているO-157は特殊で、1,000個食べただけで発症すると言われている。
腸の中では、微量元素はどのように摂取されるのだろうか。食べ物の中のいろいろな元素は、おもに腸管から吸収される。脂肪はおもにリンパに行き、タンパク質や糖は門脈に行く。門脈とは、小腸に分布している毛細血管が集まる血管で、これが肝臓につながっている。肝臓では、体内に必要なものとそうでないものを区別し、不要なものは胆汁となって便の中に捨てられる。一方、尿とともに排出される分は、いったん肝臓の中で水酸基と結びつき水溶性になってから、排出される。 |
| 【図6】作業者の有機溶剤の吸収と排泄(Ogata,1987) |
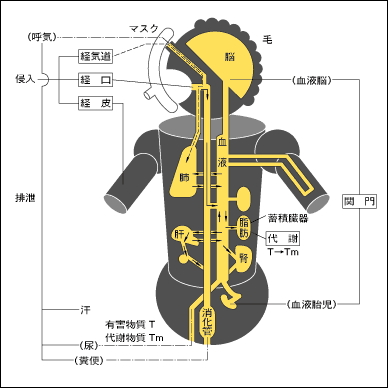 |
|
|