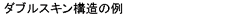アルミニウム合金製品車両の歴史
アルミニウム合金は、鉄道車両の構体(車体の主構造部分)をはじめ、内装など多くの部品に使用されています。ここでは、アルミニウム合金の構体への適用の歴史を紹介します。
アルミニウム合金製車両は、材料技術・接合技術の進歩を反映して、下のように第1世代から第4世代に分類されます。なお、同一世代であっても、車両によって構体構造は異なりますし、使用材料や接合方法も異なっていることがあります。
| 世代 | 製造初年 | 主な車両 |
|---|---|---|
| 第1世代 | 1962年 | 山陽電鉄2000系、北陸鉄道6010系 |
| 第2世代 | 1964年 | 山陽電鉄3000系、国鉄301系、営団地下鉄6000系・7000系・8000系、大阪市10系・30系・60系、 相模鉄道7000系、京阪電鉄5000系、神戸市1000形、京都市10系、名古屋市5000形 |
| 第2.5世代 | 1970年 | 札幌市2000形・6000形・7000形、国鉄381系・203系・200系、阪急電鉄7300系、神戸市3000形 |
| 第3世代 | 1981年 | 山陽電鉄3050系、営団地下鉄01系・02系・03系・05系・9000系、京阪電鉄6000系、大阪市20系・70系、 阪急電鉄7000系・8000系、京浜急行1500形、JR東海300系、東京都5300形・12-000形、 相模鉄道8000系、JR西日本300N系・500系、JR東日本E2系、札幌市8000形 |
| 第4世代 | 1992年 | 西武鉄道10000系・20000系、JR九州800系・N700系・817系、JR東海・西日本700系・N700系、 東京地下鉄10000系・15000系・16000系、京成電鉄新AE形、東武鉄道50000系、 阪急電鉄9000系・9300系、JR東日本E5系・E6系・E257系・E657系、JR西日本683系 |
第1世代
 |
 |
| 山陽電鉄2000系電車 (川崎重工提供) |
北陸鉄道6010系電車 (日本車輌提供) |
|---|
それまでの普通鋼製の構体構造はそのままで、鋼を既存のアルミニウム合金の押出形材や板材で置き換える形で車体が製作されました。1962年に製造された、図1に示す山陽電鉄2000系電車の構体構造では、押出形材のA5083合金とA6061合金が骨材として、板材のA5083合金とA5052合金が側、屋根、妻などの外板に使用されました。接合には主にミグアーク溶接が用いられましたが、外板と骨組との接合にはミグスポット溶接が用いられました。また、台枠、側、屋根、妻等各ユニットの組み立ては、アルミ合金製リベット打ちにより行われました。翌1963年に製造された北陸鉄道6010系電車では、側板、妻板はアルマイト加工(耐食性や耐摩耗性向上のため、アルミニウムの表面に酸化アルミニウムの皮膜を形成させる技術)したA6063合金押出形材を裏面で溶接して組み立てるなどして、全溶接構造となりました。

第2世代
 |
 |
 |
| 国鉄301系電車 (川崎重工提供) |
京阪電鉄5000系電車 (京阪電鉄提供) |
名古屋市営地下鉄5000形電車 (名古屋市交通局提供) |
|---|
1962年に、鉄道車両に使用することを目的として、高強度で溶接性に優れ、溶接後常温時効することにより母材と同程度の強度に回復するA7N01合金が日本で開発されました。図2は国鉄301系電車の構体構造を示しますが、A7N01合金押出形材が、高強度を必要とする台枠のはり(梁)に使用されました。他に、A5052合金、A5083合金の押出形材も使用されました。一方、板材はA5083合金が腰板などの側板や妻板に、 A5005合金が屋根板やキーストンプレート(床)に使用されました。接合は全溶接構造となり、ミグアーク溶接とミグスポット溶接(外板と柱や垂木など)が使用されました。

第2.5世代
 |
 |
 |
| 札幌市営地下鉄2000形電車 (札幌市交通局提供) |
国鉄200系新幹線電車 (国鉄発行絵葉書) |
神戸市営地下鉄2000形電車 (神戸市交通局提供) |
|---|
1969年には、9500ton押出機による、薄肉で大型のA7003合金押出形材が製作されるようになりました。図3に、国鉄200系新幹線電車の構体構造を示します。軒けた、長けたなどにA7003合金押出形材が使用され、側板、屋根板、垂木などの高強度を必要とする部材にはA5083合金の板材が使用されました。また、側ばり、横ばり、側柱など多くの部材に、A7N01合金の押出形材が使用されました。なお、接合は第2世代車両と同様な手法で施行されました。

第3世代
 |
 |
 |
| 京浜急行1500形電車 (京浜急行電鉄提供) |
JR東海・西日本300系 新幹線電車 (JR東海提供) |
相模鉄道8000系電車 (相模鉄道提供) |
|---|
1980年代初頭に、押出性に優れた(薄肉化が可能な)溶接構造用A6N01合金が開発されました。これを側板や屋根板等に使用することにより、押出形材のみで構体を構成することが可能となりました。図4に、JR300系新幹線電車の構体構造を示します。側ばりには、A6N01合金の中空押出形材が使用されています。この世代の他の車両には、床板にもA6N01合金の中空押出形材が使用されている例が多くあります。なお、1996年から製造されたJR西日本500系新幹線電車では、山陽新幹線区間での300km/h走行のため、車外騒音の侵入低減と剛性向上を目的として、側外板と床には、A6951合金を面板とコア材に用いたろう付けハニカムパネルが使用されました。
広くは、第1世代から第3世代までシングルスキン構体に分類されますが、特に第4世代と対比させて、第3世代のみをシングルスキン構体と呼ぶこともあります。接合は、第2世代・第2.5世代車両とほぼ同じですが、1998年以降に製造された車両にはFSW(摩擦攪拌接合)が適用された例もあります。
広くは、第1世代から第3世代までシングルスキン構体に分類されますが、特に第4世代と対比させて、第3世代のみをシングルスキン構体と呼ぶこともあります。接合は、第2世代・第2.5世代車両とほぼ同じですが、1998年以降に製造された車両にはFSW(摩擦攪拌接合)が適用された例もあります。

第4世代
 |
 |
 |
| 西武鉄道20000系電車 (西武鉄道提供) |
東京地下鉄10000系電車 (東京地下鉄提供) |
JR東日本E5系新幹線電車 (JR東日本提供) |
|---|
A6N01合金の大型中空押出形材により構体全体が構成されるようになり、形材自体が高い剛性をもっているため、柱、垂木などが不要になりました。また、部品点数が減ったことにより、構体の組み立てが容易になりました。この構体をダブルスキン構体と呼んでいます。図5は、東京地下鉄10000系電車の構体図を示します。この車両では、一部の補強を除いて、大部分の部材にA6N01合金押出形材が使用されています。第4世代の車両では、形材の接合にはFSWが広く採用されています。