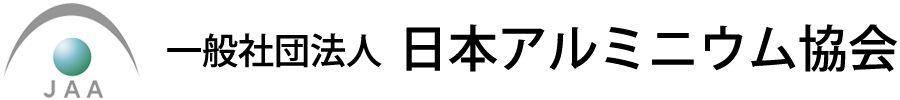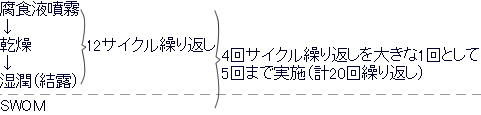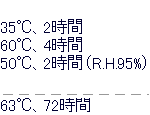酸性雨に対するカラーアルミの耐久性
分野別ページ|建築・土木
酸性雨に対するカラーアルミの耐久性
1.はじめに
酸性雨は最近話題になっていますが、歴史を振り返れば現象自体目新しいものではありません。即ち、日本国内を例にとりますと、明治 時代の足尾銅山の例(亜硫酸ガスによる土壌の酸性化と、それに伴う木の枯れ)や、別子銅山新居浜精錬所の四坂島への移転 (現象は足尾と同じ)、さらに近年になると昭和40年代に顕在化した川崎、四日市で代表される大気汚染等があげられます。
これらは国内だけの問題ですが、現在話題になっているのは”越境する公害”としての側面であり、日本の場合は中国の影 響が大きいとされています。なお、酸性雨とは、蒸留水に二酸化炭素を飽和させたときのpH5.6より酸性になっている雨をいいます。
2.酸性雨の影響についての実験
酸性雨に対する影響を調べるため各種の促進試験方法が提案されています。ここではそれらによる試験に加え、東京及び大阪で 行った酸性雨に対するばく露試験結果との対応について検討した結果を紹介します。
1 供試材、試験方法及び評価方法
供試材は表1に示すように、カラーアルミを2種類、比較材としてカラー鋼板及びカラーステンレス、アルミニウム合金の無処理材と 陽極酸化処理材(アルマイト)を使用しました。なお、塗装材については促進試験、ばく露試験とも試験前に素地に達するクロスカットを 入れ、試験に供しました。
促進試験条件を表2に示します。酸性雨サイクル腐食試験(CCT:Cycle Corrosion Test)に促進耐候性試験であるサンシャイン ウェザオメーター(SWOM)を組み合わせた複合耐久試験です。腐食液は「H2SO4(96wt%)17.3mℓ、HNO3(61wt%)12mℓ、 NaCl 500g、蒸留水 10ℓ」のpH3.5に調整したものを用いました。また、SWOMを含まない塩水噴霧CCTや酸性雨CCTも比較試験と して実施しました。
屋外ばく露は東京都新宿区と大阪府堺市にて最大5年間実施しました。雨水のpHを調査した結果、大阪の場合は時期によって酸性 雨になったりならなかったりしていましたが、東京では常時酸性雨となっていました。
耐食性の評価は表面観察とクロスカット部からのふくれ幅で行いました。
表面処理の耐候性は、汚染物を除去後、光沢保持率及び色差測定で評価しました。
表1 供試材の仕様
| 種類 | 材質、板厚(mm) | 使用塗料及び膜厚 | 上塗色相 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| プライマー | 膜厚 (μm) | トップコート | 膜厚 (μm) | |||
| カラーアルミ1 | A5052P-H34 0.8t | エポキシ | 5 | ポリエステル | 15 | アンバー |
| カラーアルミ2 | A3005P-H24 0.7t | エポキシ | 5 | ポリふっ化ビニリデン | 23 | チョコレート |
| カラー鋼板(3コート) | 5%Al-Znめっき鋼板 0.4t | エポキシ | 5 | ポリふっ化ビニリデン | 30 | チョコレート |
| カラーステンレス | SUS304 0.4t | エポキシ | 4 | シリコンポリエステル | 16 | チョコレート |
| 無処理(アルミニウム) | A5052P-H34 0.6t | – | – | |||
| 陽極酸化処理 | A1100P-H14 1.5t | 硫酸皮膜(膜厚18μm)、酢酸ニッケル封孔 | シルバー | |||
表2 複合耐久試験の試験条件
| サイクル条件 | |
|---|---|
| サイクル内容及び繰り返し数 | 温度、時間 |
|
|
|
2 試験結果
1)促進試験間の比較:塩水噴霧CCTと酸性雨CCT及び複合耐久試験の比較
表3に135サイクル後の塩水噴霧CCTと酸性雨CCT及び3回サイクル(噴霧サイクルは144サイクル)の複合耐久試験後の表 面状況を比較しました。
腐食促進性は腐食液が酸性である酸性雨CCTや複合耐久試験が、塩水噴霧CCTより大きく、表面処理毎の耐候性の差及び ふくれは複合耐久試験で顕著になりました。
表3 各種試験後の促進性比較:表面状況
| 供試材 | トップコート もしくは 表面処理 | 試験方法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩水噴霧CCT | 酸性雨CCT | 複合耐久試験 | |||||
| 平面部 | カット部 | 平面部 | カット部 | 平面部 | カット部 | ||
| カラーアルミ1 | ポリエステル | ○ | ○ | シミ斑点 発生 | ○ | わずかに 変退色 | わずかに 腐食 |
| カラーアルミ2 | ポリふっ化ビニリデン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 微細なふくれ わずかに腐食 |
| カラー鋼板 (3コート) | ポリふっ化ビニリデン | ○ | 白色腐食 生成物発生 | ○ | 白錆発生 | ○ | ふくれ発生 腐食発生 |
| カラーステンレス | シリコンポリエステル | 変色 光沢減 | 赤錆発生 | 変色 光沢減 | 赤錆発生 | 変退色 光沢減 | わずかに腐食 |
| アルミニウム 合金 | 無処理 | 変色 光沢減 | – | 変色 光沢減 | – | 腐食発生変色 光沢減 | – |
| 陽極酸化処理 | 硫酸皮膜 (膜厚18μm) | ○ | – | 小ピット発生 | – | ○ | – |
表面処理の差を複合耐久試験から判断すると次の順序となります。
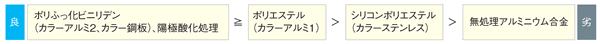
ただし、ポリふっ化ビニリデン塗装板は鋼板、カラーアルミとも塗膜のふくれが発生しやすい傾向があり、特に鋼板で顕著でした。
これはポリふっ化ビニリデンの場合、塗膜の透湿性が低いため、いったん腐食性因子が塗膜内に浸入すると残存しやすいものと考えられます。そのような状況下では素材自身の耐食性の差が顕著になるものと判断されます。
素材自体では言うまでもなくアルミニウム、ステンレスが優れていました。
2)屋外ばく露試験結果及び複合耐久試験との相関
屋外ばく露5年経過時点で東京、大阪ともカラー鋼板(ポリふっ化ビニリデン)のクロスカット部に塗膜のはく離がみられました。その他の材料では無処理アルミニウム合金に腐食がみられただけでした。
複合耐久試験結果とばく露試験結果を比較した結果、光沢保持率、色差ともかなり良い一致を示しました。
図1 各種試験の促進性比較:光沢保持率及び色差
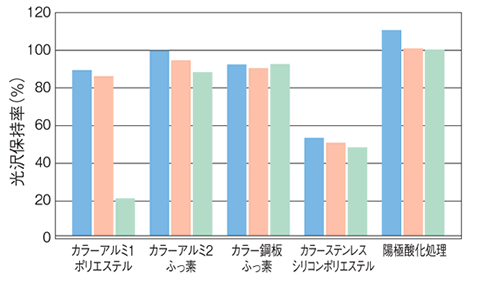
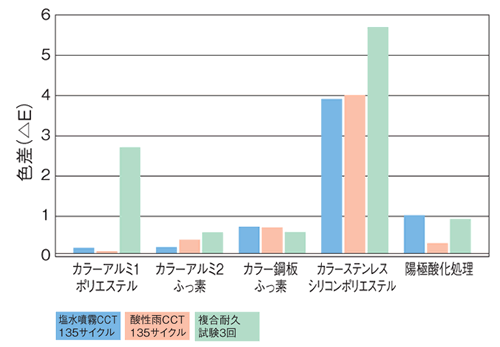
3.まとめ
以上の結果をまとめると次の通りです。
- 光沢および色調の変化で耐久性を考えた場合、素材そのものの差よりもトップコートの差が現れており、ポリふっ化ビニリデンが陽極酸化処理(アルマイト)と並んで最も優れていました。
ただし、ポリふっ化ビニリデンはクロスカット部に”ふくれ(はく離)”が発生しやすい傾向がありました。
塗膜に疵が入った場合を考えると、なるべく耐食性の良い材料の方が好ましいと考えられます。
検討した促進試験のなかでは、酸性雨CCTにSWOM(サンシャインウェザオメーター)を組み合わせた複合耐久試験が、塗膜の外観変化を含めて実際のばく露とかなりよく対応していました。