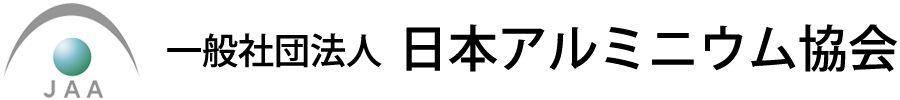5.一般取扱い
分野別ページ|建築・土木
5. 一般取扱い
1. 製品の保管
一般に鋼材を取扱うときよりていねいにしたい。アルミニウム製品は表面が美しいだけに,その取扱い方法を誤ると,表面に傷がつきやすく,軽微な汚れや腐食が発生する。もっとも留意しなければならないことは“湿気”と“ほこり”である。
実際の保管はつぎの要領で行うことが望ましい。
※スマートフォンの場合は横にスクロールしてご確認頂けます。
| 水 濡 れ、 結露 に 注意 | 1) 散水,雨漏れ等により製品を濡らすことは絶対に避けること。 |
| 2) 窓や出入口付近での保管は極力避けること。これは,外気温の急激な変化によって製品の表面に結露をおこし,腐食の原因となる。 | |
| 3) 冷たい材料を高温多湿の工場などに移す場合には,あらかじめ乾燥した場所に一度中置きして,材料の実体温度が上昇してから移すべきである。 | |
| 保管に 注意 | 1) ほこりのたたない床張り倉庫に保管し,屋外放置はしないこと。 |
| 2) 保管場所は平担な所を選ぶこと。傾斜している場所に段積みすると変形を生じる可能性があり,安全に関しても危険である。 | |
| 3) 倉庫内の換気は晴天時の日中に行い,雨天時または夜間は避けること。 | |
| 4) 倉庫内の気温は外気の露点以上に保持できれば理想的である。 | |
| 5) 材料の長期保管を避けること。長期保管をする場合は時々点検し,腐食を未然に防止する配慮が望ましい。 | |
| 6) 段積み保管に際しては,同一製品寸法に限り大板は2 m以下,小板は1.5 m以下とし,脚を揃えて積重ねること。 | |
| 7) 表面傷防止や成形性の向上を目的とした表面保護フィルムを貼合わせた製品は,直射日光の当たらない屋内に保管し,表面保護フィルムを貼りつけた状態で長期間保管しないこと。長期保管によって表面保護フィルムが劣化し,剥離困難等の原因となる。 |
2. 製品の取扱い
外気温や湿度の変化で材料の表面に結露が発生し,放置しておくと白い花模様の腐食が生じる。
※スマートフォンの場合は横にスクロールしてご確認頂けます。
| 運搬、 移動に注意 | 1)運搬,移動は1包装単位ごとに行うこと。 2)製品を移動させる場合は,フォークリフトまたはスタッカークレーンを使用し,パレットの下部をささえて運搬することが望ましい。 3)クレーンを用いて玉掛で運搬する場合は,ナイロンスリング等を使用すること。スチールワイヤ-を用いる場合は,端部をいためないように緩衝材を当てること。また,長尺製品を玉掛で吊る場合は包装品の曲がりを防ぐために,玉掛位置は3支点以上とすることが望ましい。 |
| ハンドリングに注意 | 1)包装品を1個ずつ扱う場合,製品を曲げないようにすること。板製品で曲がるおそれのある場合はたてて取扱うと比較的曲がらない。 2)製品の積みかえ,その他の移動はできるだけ少なくし,運搬,移動に際しては,製品のおどりを防止するために必ず拘束すること。 3)合紙なし包装を個装ごとにハンドリングする場合は,モミ傷防止の観点から特に一人で扱う場合に製品をたわませないように注意する。 |
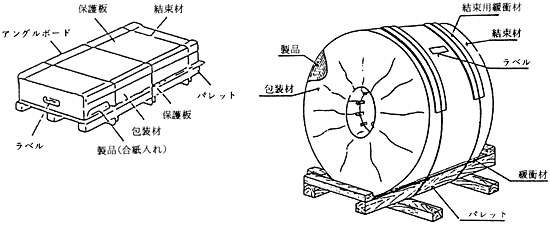
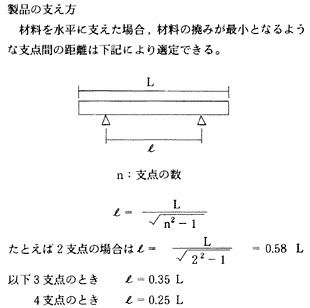
3. 製品別取扱い
アルミニウム板建材を製品として使う場合の取扱い方法は下記の通りである。
※スマートフォンの場合は横にスクロールしてご確認頂けます。
| 生 地 材 | アルミニウム製品は他の金属製品に比べ素地がきれいなため傷がつくと目立ちやすく,とくに美観を重視する場合には取扱いに十分注意する必要がある。指紋などがついた場合はなるべく早くケトン,ベンゾールでふきとる。大気中では保護酸化皮膜が表面に形成されるので,内部まで腐食が進行することは少ないため,機能的には長期間の使用に十分耐える。湿気が多いと表面がいくぶん粗面化することがあり,光沢が落ち,白色ないし灰色を呈する。 |
| アルマイト材 | アルマイト材の酸化皮膜の膜厚は普通6~15μm程度である。この酸化皮膜自体は非常に硬いため,曲げたり,強い衝撃を受けると,その部分の皮膜にクラックが発生するので注意しなければならない。しかし皮膜全体が落ちるようなことはないので,その点についての心配はない。皮膜自体の耐摩耗性は強いが,洗浄する場合はなるべく軟らかいスポンジ,布などを用い水洗する。また洗剤を用いる場合はアルカリ性のものは避け,中性のものを用いる。付着した油脂類はアルコール,ケトン,ベンジン,ベンゼンなどでふきとるとよい。 |
| 塗 装 材 (カラーアルミ) | 塗装面に付着した粘着性のある煤煙や油類は洗浄によって洗い去る。洗浄剤は水溶性で中性のものを用いる。 |
4. 結露対策
※スマートフォンの場合は横にスクロールしてご確認頂けます。
| 予 知 | 1)製品の温度と外気の霧点の関係であるから,毎日の天気予報に注意する。 2)春先,梅雨時,秋口台風通過時および工場が長くとまり,冷えきっている正月休み時などに集中する。 3)結露警報装置で危険状態を予測する。 |
| 予知した 場合の処置 | 1)外気の影響の少ないところ,あるいは空気の乾燥している炉の周辺などへ移動する。 2)移動できない場合は熱風ブロアをかけ,コイルの実体温度を上昇させる。 3)コイルの端部の目張りなど簡易包装を行なうことにより被害を最小限にとどめる。 |
| 発生後の 処置 | 1)自然に乾燥させ,水分が蒸発してから乾布で拭きとる。 2)水分の付着面を手や布でこすると,しみのできる範囲が広がるので注意する。 3)結露によるしみや腐食はスコッチブライト,ワイヤーブラシーなどにより除去・修正することができる。 |