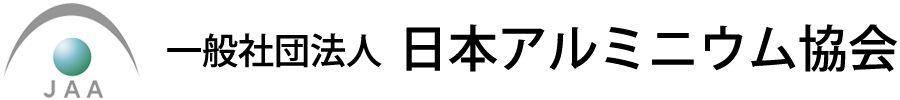9.使用上の留意点
分野別ページ|建築・土木
9. 使用上の留意点
アルミニウムを建材として使用する場合,アルミニウムの持つ特性をよく把握し,アルミニウムにあった施工をする必要がある。以下に主として屋根・壁の具体例で説明する。
1. メンテナンス
アルミニウム塗装品では,美観を保つために再塗装することがあるが,素地アルミニウムが耐食性に優れる材料なので,防食の意味での再塗装は殆ど必要としない。塗装面,アルマイト面,生地面の美観を保つには,定期的に表面を水洗することが効果的である。中性洗剤を少量溶かした水を浸したやわらかい布,又はスポンジで水洗し,仕上げに真水で水洗する。
2. 熱 膨 張
アルミニウムは一般的に熱膨張が大きくその対策,処理が難しいと考えられているが,その線膨張係数は銅の約2倍にしか過ぎず,その伸縮量は構造物に生じている通常の変位量と比較して決して大きなものではない。
例えば1m長さのアルミニウムが常温から50℃昇熱すると約1.2mm伸びるが,変位量の上では建築物として特にあらためてその対策を考慮しなければならない程のものではない。ただ,外気温,直射日光にさらされる長尺の外装材の場合,伸縮を前提とした構法がよい。例えば,ボルト・ナットで止め付ける場合,下穴径を大きくとり,目地部はこれに見合う伸縮吸収幅を考慮したり,パネルの固定金具への緊結は膨張方向へルーズになるようにとりつけたりする。
3. 接触腐食
アルミニウムと銅などのように異種金属どうしが接触する工法の場合,水分が存在すると金属が一種の電極となり,電気化学反応をおこす。この時電位系列で卑な金属,この場合アルミニウムが溶け出すがこの現象を接触腐食という。例えばアルミニウム屋根の場合,取付部,役物,釘 ボルトなどにアルミニウム以外の金属を使用することが多く,接触腐食を防止する手段を講ずる必要がある。
一般的な対策
①異種金属間を電気的に絶縁する。
・相手異種金属側に絶縁効果のある表面塗装を施す。
・相手異種金属側にステンレス,クロムめっき材など表面が不働態化されている材料を使用し,かつ絶縁する。
・ビニールテープのような透湿性のないテープやコーキング材を使用する。
・アスファルト系またはジンクロメード系塗料などを使用する。
②亜鉛めっき材などのような電位の卑な金属を使用する。
③水分を存在させない。
具体的対策例
①心木なし長尺瓦棒葺の吊子
アルミニウムを使用することが望ましい。強度的配慮で,カラー鉄板,亜鉛鉄板が使われているが,曲げおよび切断小口からの接触腐食も報告されている。小口部分への絶縁対策を講じて欲しい。
②心木あり長尺瓦棒葺のキャップ止釘
アルミニウム,ステンレス,亜鉛めっき釘を使用すべきで,銅,鉄,真鈴釘の使用は避ける。
③アルミニウム折板のタイトフレーム,ボルト
タイトフレームは電気亜鉛めっき(JIS H 8610)又は溶融亜鉛めっき(JIS G 3302)を施した鋼材を,ボルト・ナットは電気亜鉛めっき(JIS H 8610)を施した鋼ボルト・鋼ナットまたはアルミ合金製,ステンレス製を使用する。固定金具は溶融亜鉛めっき鋼板の塗装材または,ステンレス製などを使用する。(金属製折板屋根構成材 JIS A 6514)
④その他
二階雨樋や二階屋根が銅,亜鉛鉄板で一階屋根がアルミニウム生地板材の場合,直接接触していなくとも,雨水に溶解した銅,鉄がアルミニウム上に作用して接触腐食をおこすことがある。材料の統一使用をおすすめしたい。
4. 結 露
一般に金属屋根の場合,非金属屋根材(瓦,石綿スレート)に比べ,板厚が薄く熱伝導率が大きいため屋外側と屋内側の温度差がほとんどなく結露が発生しやすく,結露防止策を施す必要がある。結露すると金属の裏面からの腐食発生の要因となる。
断熱材を使用することなどにより結露防止を図れば実用上心配はない。ただ,金属屋根材の場合,本質的には断熱性は乏しく結露が発生しやすいため,結露が生じても裏面からの腐食をおこしにくい材料が屋根材には望ましい。この意味においてはカラー鋼板よりはアルミニウム板,アルミニウム板よりは裏面にも塗装の施されているカラーアルミが望ましい。
5. 防 火
①アルミニウムは,建築基準法第2条第9号の規定により不燃材料である。
②表面に発煙性のある化粧塗膜層のあるカラーアルミは,建築基準法施行令第108条の2に掲げる性能を有するものとして,「NM-8597」及び「NM-8598」(板厚0.3mm以上0.5mm未満)として不燃材料に認定されている
表27 代表的なカラーアルミ不燃材認定会社および商品名
| 社 名 | 商 品 名 |
| 古河スカイ(株) | 古河カラーアルミ,古河カラーアルミE,フルフロン,フルフロンE スカイコート,スカイコートEM,スカイフロン,スカイフロンEM |
| (株)神戸製鋼所 | アルカラー,アルカラーアート |
| 三菱アルミニウム(株) | ダイヤカラー,ダイヤカラーエンボス |
| 日本軽金属(株) | 日軽カラーアルミ,日軽カラーアルミエンボス,日経フロルカラー,日軽アルフロンエンボス |
| 住友軽金属工業(株) | スミカラー,スミケイフロン |
カラーアルミ不燃材の仕様 NM-8597
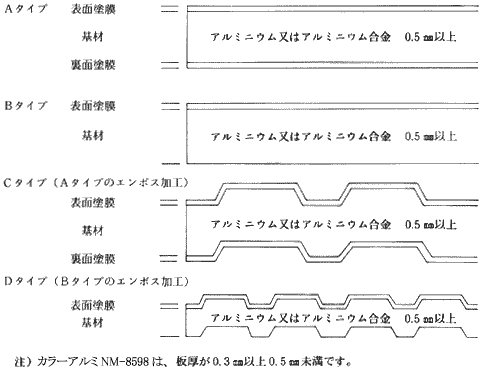
基 材
基材には,JIS H 4000(アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条)に規定するアルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条並びにこれに準ずるもので,かつJIS H 4000に規定するA5052Pの融点以上の合金成分のものを使用する。
塗料の種類および重量
表25に示す塗料を用いて工場塗装を行う。
塗料は異なった種類の塗料を二層以上塗装し,焼付けることができる。ただし,最終仕上がり塗膜中における有機質量は表28に示す塗料種類ごとに算定した有機質量算定値の合計が片面65g/m2を超えてはならない。
表28 塗料種類ごとの有機質量算定値
| 塗 料 の 種 類 | 有機質量算定値(g/m2) |
| アクリル樹脂系塗料 | 乾燥塗膜重量g/m2×塗膜中有機質含有率(W%) |
| ポリエステル樹脂系塗料 | 乾燥塗膜重量g/m2×塗膜中有機費含有率(W%)×65/60 |
| シリコン樹脂系塗料 | 乾燥塗膜重量g/m2×塗膜中有機質含有率(W%) |
| 塩化ビニル樹脂系塗料 | 乾燥塗膜重量g/m2×塗膜中有機質含有率(W%) |
| ふっ素樹脂系塗料 | 乾燥塗膜重量g/m2×塗膜中有機質含有率(W%) |
| エポキシ樹脂系塗料 | 乾燥塗膜重量g/m2×塗膜中有機質含有率(W%)×65/50 |
カラーアルミNM-8598の塗料種類・有機質量としては,ポリエステル樹脂系(20g/m2)とフッ素樹脂系(30g/m2)のものが認定品となっている。
防火構造
次のものが建築基準法施行令第108条により防火構造(屋根)として認められている。
・木毛セメント板の上にアルミニウム板を葺いたもの。ただし,たる木は準不燃材以上の防火性能を持った材料……例えば軽量形鋼……を使うか,または軒裏を防火構造……例えばラスモル20mm以上……とすること。
・アルミニウム屋根材に直接とりついているたる木,またはもやが不燃材料……例えばH形鋼……である場合のアルミニウム葺き屋根。
このような構造は現在広く行われているごく通常のものであり,逆にいえば,特に変わった新しい考え方を採り入れない限り,防火構造としてのアルミニウムは問題ない。
防火構造外壁(30分)
カラーアルミ+モルタル塗+木毛セメント板(0.5mm+5mm+18mm)で個別認定を取得したものがある。「PC030NE-9102」
6. シーリング材
シーリング材とは,カーテンウォール,パネルなどの建築構成材の目地部分および各種防水工事などに使用されるものである。
①シーリング材の選び方
より適切なシーリング防水工事を行うには,建物の規模・種類からくる要求性能に対して目地に求められる諸機能を踏まえたシーリング材を選び出すことが基本であるが,この他,シーリング工事の適正な予算,シーリング工事そのものの適正な条件など,設計から工事に至る環境を全体的に勘案して選定することが肝要である。
②シーリング材は使用部位によって適合材料の選定が重要である
| シーリング材の種類 被 着 体 | シリコーン | 変成シリコーン | ポリサル ファイド | |||
| 2成分形 | 1成分形 | 2成分形 | 2成分形 | |||
| 金属 カーテンウォール | ノックダウン方式 | ◎ | ||||
| パネル方式 | パネル目地 | ◎ | ○ | ○ | ||
| 各種外装パネル | 樹脂鋼板・塗装鋼板・ ほうろう鋼板目地 | ○ | ◎ | |||
| 金属製建具 | サッシ間目地(水きり, 皿板目地を含む) | ◎ | ○ | |||
| 笠 木 | 金属笠木目地 | ◎ | ||||
| 耐 久 性 区 分(1) | 9030 | 8020 | 9030 | 9030 | ||
◎:最適シーリング材 ○:使用可能シーリング材
注(1) 耐久性区分は,JIS A 5758(建築用シーリング材)による。