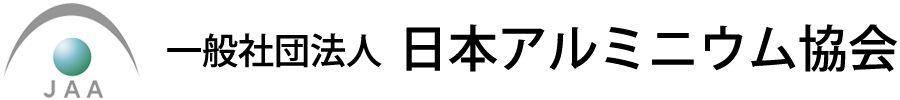10.設計例
分野別ページ|建築・土木
10. 設 計 例
アルミニウム板を使用し,屋根およびサイディングを設計・施工する場合の具体例を,下記に紹介する。
1. アルミニウム屋根
①屋根材および付属部品の選定について
1) 一般にアルミニウム合金JIS H 4001に規定するA3005P-H24またはH26のカラーアルミの板厚0.4~0.6mm(但し,折板ぶきの場合は0.6mm以上)を使用する。また,屋根の装飾を必要としない場合は,表4に示した屋根材料の無塗装アルミニウム板を使用する。
2) 吊子の材料は,接触腐食を考慮して冷間圧延ステンレス鋼板または塗装ステンレス鋼板の0.4mm板厚を使用するのが望ましい。但し,鋼板類を使用する場合には,両面塗装カラー鋼板を使用する必要がある。
3) 役物の材料は,表4に示すアルミニウム合金を使用し,板厚は屋根板と同等か1ランク上を用いる。
4) 一般に強度を向上する必要がある場合には,コスト・施工性を考慮し板厚を上げるより取付けピッチを小さくした方が良い。
5) 屋根材料の留付けに用いる金物は,
・表27に示すアルミニウムおよびステンレス製の密閉型ブラインドリベット
・図9に示すステンレス製タッピンねじ(屋根材の板厚が0.8mm以上の場合に限る。)
・ステンレス釘(スパイラル付き)
などとすることが望ましい。
6) 折板葺きの場合は,JIS A 6514に詳細が規定されているので参照願いたい。
表30 ブラインドリベットの種類
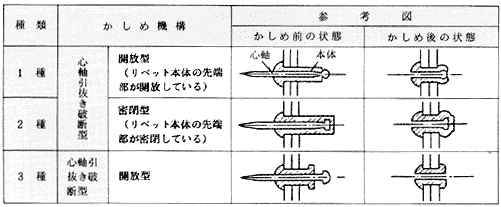
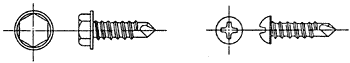
図9 セルフドリリングタッピンねじの形状
②アルミニウム屋根の各種構法について
アルミニウム屋根の構法には心木あり・なし瓦棒ぶき,立平ぶき,蟻掛ぶき,波板ぶき,横ぶき,金属成形瓦ぶき,一文字ぶきや段ぶきなどが一般的であり,鋼板に使用される屋根ぶき構法と同様に適用可能である。なお,心木なし瓦棒ぶきについては,アルミニウム押出形材を併用した工法もある。これは,耐久性の向上や異種金属との接触腐食防止になる。
図10~図16に,代表的な構法例を示す。(亜鉛鉄板会発行,鋼板製屋根構法標準より抜粋)
③アルミニウム屋根の設計施工について
アルミニウム板葺工法は,透水性がなく不燃材料で軽量なため施工が容易であり,素材が耐食性に優れるためメンテナンスフリーである。但し,屋根が軽量になるため耐風圧計算の上からも屋根勾配などにより配慮するとよい。
屋根の設計施工に当たっては,耐風強度 防水性能などについて,下記事柄を十分注意する。
・はぜ,吊子,釘,ボルトなどによる接合部分
・けらば,軒,棟などの各部分
・屋根の下地
・働き幅(固定のためのピッチ)
・シーリング方法の設定
心木あり瓦棒ぶきの例
心木あり瓦棒ぶきは、図10のように、溝板が心木を持つ瓦棒を介して下地に止めつけられた構法をいう。
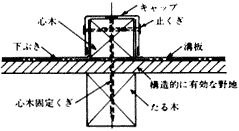
図10 心木あり瓦棒ぶき
心木あり瓦棒ぶきは、キャップ(瓦棒包み板)と溝板をくぎで心木に止めつける構法で、たる木を有する屋根下地に適している。主に、木造の住宅や小規模の建物で、10/100以上の勾配の屋根に用いられる。
心木なし瓦棒ぶき(部分吊子)の例
心木なし瓦棒ぶき(部分吊子)は、図11のように、溝板が心木を持たない瓦捧内の部分吊子を介して下地に止めつけられた構法をいう。
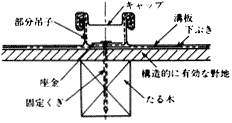
図11 心木なし瓦棒ぶき(部分吊子)
心木なし瓦棒ぶきの適し吊子構法は、たる木がなく野地を敷き込んで直接もやに接合する屋根に適した構法である。
鉄骨造のやや大規模の建物で、5/100 以上の勾配の屋根に用いられる。
心木なし瓦捧ぶき(通し吊子)の例
心木なし瓦棒ぶき(通し吊子)は、図12のように滋養板が心木を持たない瓦棒内の通し吊子を介して下地に止めつけられた構法をいう。
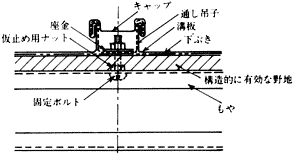
図12 心木なし瓦棒ぶき(通し吊子)
心木なし瓦棒ぶきの適し吊子構法は、たる木がなく野地を敷き込んで直接もやに接合する屋根に適した構法である。
鉄骨造のやや大規模の建物で、5/100 以上の勾配の屋根に用いられる。
立平ぶきの例
立平ぶきは、図13のように、溝板の立はぜを介して下地に止めつけられた機法をいう。
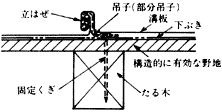
図13 立平ぶき
立平ぶきは、瓦棒ぶきの瓦棒に相当する部分が、巻はぜ形式の立はぜとなったものである。
意匠的に繊細な感じになる点が特徴であるが、耐風強度は心木なし瓦棒ぶきに劣る。
この構法は、木造住宅のような小規模の屋根で、5/100 以上の勾配の屋根に用いられる。
蟻掛ぶきの例
蟻掛ぶきは、図14のように、溝板の立はぜと蟻を介して下地に止めつけられた構法をいう。
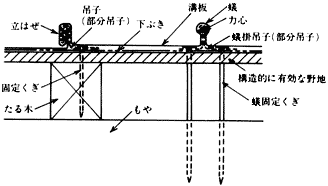
図14 蟻掛ぶき
蟻掛ぶきは、立平ぷきの変形で、立平ぶきの場合と同様な屋根に用いられる。
波板ぶきの例
波板ぶきは、図15のように、波板が直接下地に止めつけられた構法をいう。
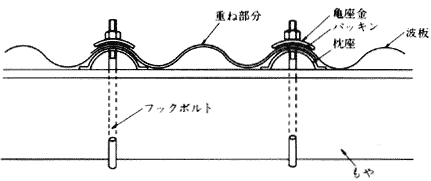
図15 波板ぶき
一般に用いられる波板の断面形状は、JIS G 3302及びJIS G 3312に規定されている。
この波板ぶきは、野地を省略してもやに直接ふくことのできる構法であるため、最も簡単な屋根といえる。
しかし住宅にはあまり用いられず、工場や仮設的な建物などで、30/100以上の勾配の屋根に用いられる。
波板ぶきは、図15のように、波板が直接下地に止めつけられた構法をいう。
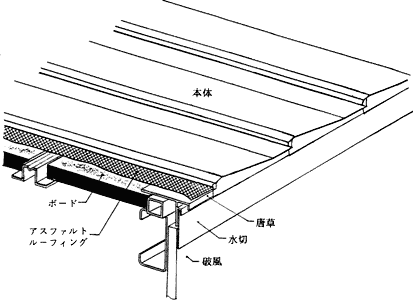
図16 横ぶきの例
1)軒先部分の取合い
軒先が水上側の場合は,片流れ屋根の上部軒先では雨水が桟鼻部から浸入するため,図18の様にはぜ部を倒した形状にし,雨水を先端部分で排除する。(唐草部も逆勾配になっているので,コの字状にする。)
また,屋根勾配が緩く軒先が水下側の場合は,唐草の形状と取付けを図20の様にする。
更に,屋根が長尺で勾配が緩く雨量が多い場合には,唐草の捨て部のむだ折りは役立たないため,図21の様な納め方とする。
2)吊子の使い方
吊子の取付に当たっては,強度と屋根勾配などιこより部分吊子と通し吊子の2種類がある。
吊子の形状は,各屋根構法に応じて異なるが,代表的な事例を図22~23に示す。
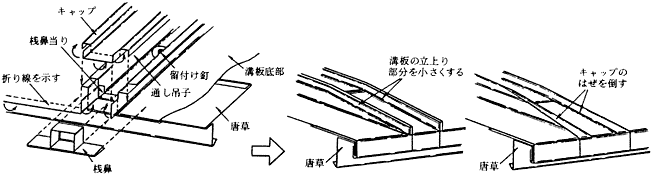
図17 軒先の納め方 図18 片流れ水上の軒先の納め方
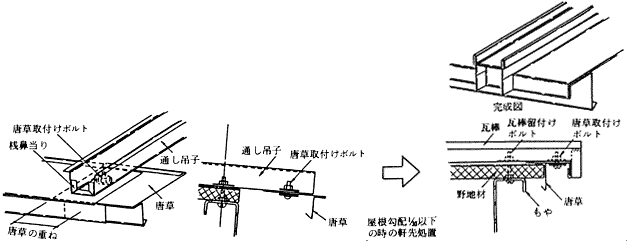
図19 軒先唐草の取付け方 図20 唐草の取付け方法
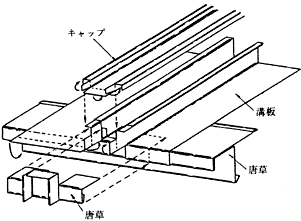
図21 緩勾配用の軒先納め
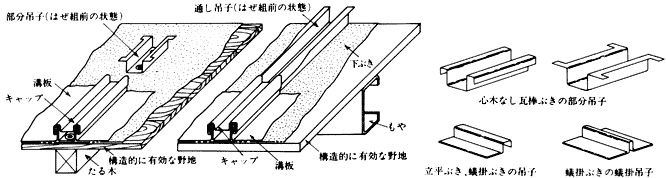
図22 吊子の使い方の例 図23 他屋根構法の吊子
④折板屋根構法について
1) 特徴
・野地板などの下地材を用いない屋根構法である。
・適用可能な屋根の形状は,片流れ,招き,切妻,ろく屋根であり,曲面的な屋根には不向きである。
2) 設計のポイント
・折板のウェブの長さが大きい(幅厚比)と,荷重が加わったときに変形が生じ易い。これは,梁と同様に上下緑周辺に正負の応力が大きく発生し折曲げ部に集中するためである。このため山高と板厚との関係がJIS A 6514に規定されている。図24に折板の単体図を紹介する。
・各荷重に対する耐力,防水性能,その他故障の原因となるので,安易に板厚の低減は避けるべきである。
3) 折板構成
・折板屋根の概略構成図および断面形状事例を,図25,図26に示す。
4) 接合用部分の材質
・タイトフレーム,固定ボルト・ナット,座金などは,SUS 304とする。
・パッキンは羊毛長尺フェルトにアスファルトを十分に含侵させる。
5) 軒先廻り
・折板は,屋根勾配がゼロに近いため,軒先は雨水の一部が折板の裏側に伝わって室内に浸入することがある。このため,防止策として折板の軒先に尾垂れを付ける。具体例を図27,図28に示す。
6) 排水の落しロ
・設計のポイントとして,折板の耐力的に悪い影響を与えないこと,雨水が完全に排出できる位置などが挙げられる。この事例を,図29に示す。
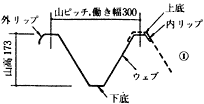
図24 折板の単体図
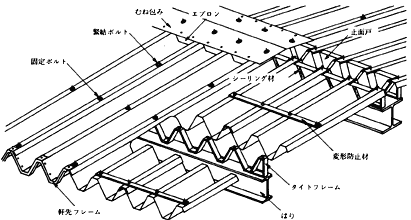
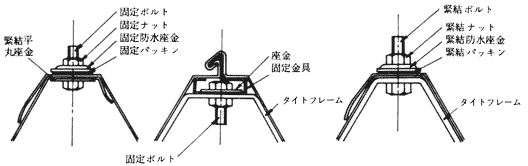
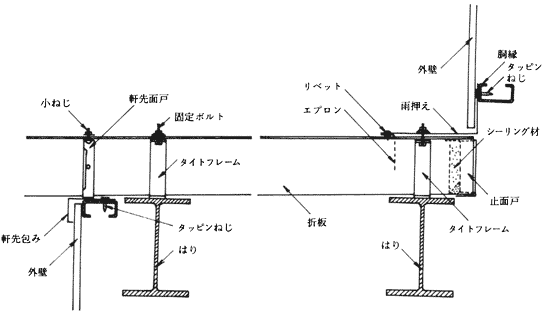
図25 折板屋根の概略構成図
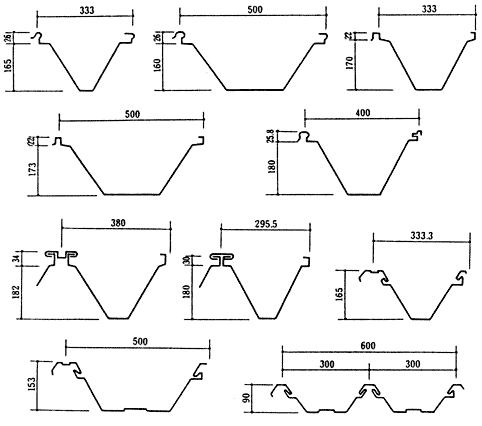
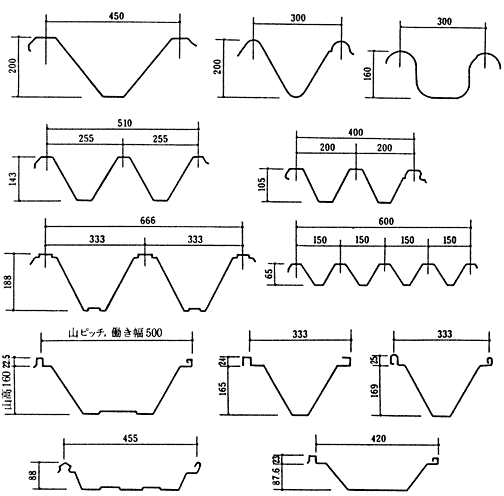
図26 折板の断面形状図の例(単位:mm)
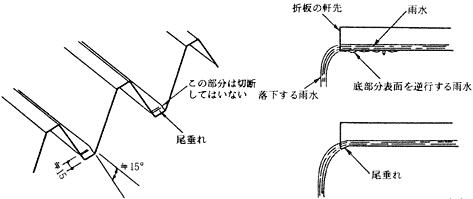
図27 尾 垂 れ 図28 尾垂れの効果
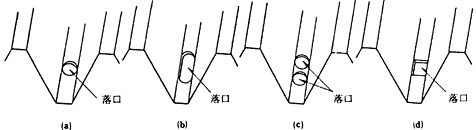
図29 落口の開け方
①曲げ耐力は落口がない場合の80%に低下する。
②曲げ耐力時のたわみ量は,落口がない場合と大差ない。
2. カラーアルミサイディング
①サイディングおよび付属部品の選定について
1)一般にアルミニウム合金JIS H 4001に規定するA3003P-H14,A3005P-H24など主としてAl-Mn系合金(表4参照)カラーアルミの板厚0.4mm前後を使用する。
デザイン性および強度上の配慮から,エンボス加工材が使用される場合がある。また,図30に示すような裏打ち材を断熱および遮音,防火などの目的に応じて貼付けるのが普通である。
2)出隅,入隅などの役物には,一般にサイディングと同様のカラーアルミをベンダー曲げやロールフォーミングにより成形した部材または塗装を施したアルミ押出形材を使用する。
3)サイディングの留付けには,一般にアルミ釘,ステンレス釘を用いる。但し,下地材料によっては,ステンレス製セルフドリリングねじを使用する場合もある。
図31にカラーアルミサイディング工事に使用される代表部品図を示す。
②カラーアルミサイディングの各種構法について
カラーアルミサイディングの構法は,横張り・縦張りなどが一般的である。
図32と図33に,代表的な構法例を示す。
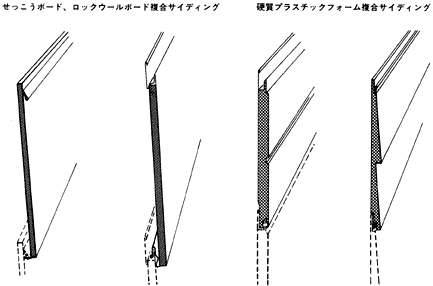
図30 横張りの例
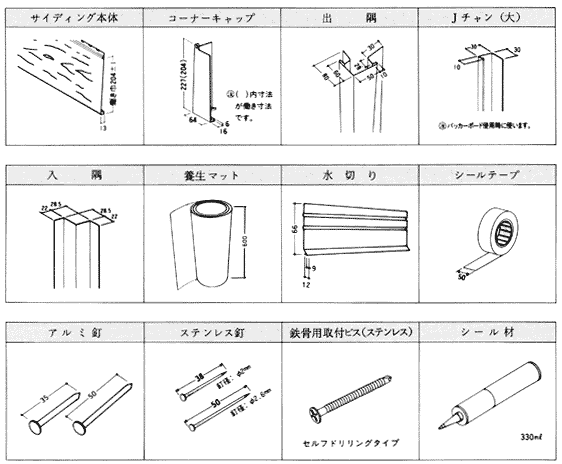
図31 代表部品図
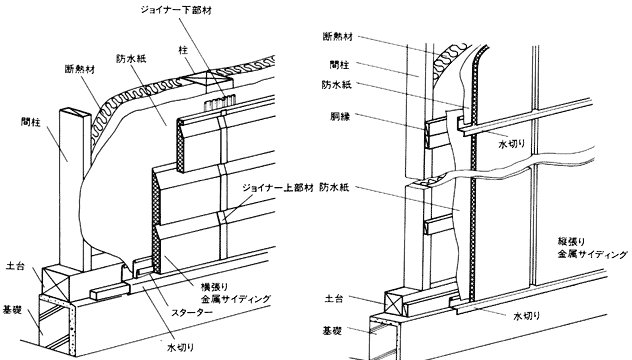
図32 横継ぎジョイナー 図33 縦継ぎ部分の納め方
(金属サイディングの表面形状と同じ)
③カラーアルミサイディングの設計施工について
カラーアルミサイディグは,軽量なため施工が容易であり,素材の耐食性に優れるため表面のデザイン性を保持できメンテナンスフリーである。カラーアルミサイディングの具体的な特徴を,以下に示す。
・軽量であるため留め付けが簡単である。
・表面仕上げ材,裏打ち材の種類によって難燃性,防火性が異なる。
・表面仕上げは,プレコートであるため耐久性が良い。多少の傷が付いても錆が生じない。
・水分を含有しないため,凍害の心配がない。
・接合部の形状に優れるため,防水性が良い。
カラーアルミサイディングの設計に当たっては,下地材料(木造,鉄骨など)やサイディング構法の組合せに応じた取付け方法や胴緑を用いる。特に,木造の胴縁材は十分に乾燥したものを使用し,間隔は455mm以下とする。また,防火構造が要求される場合には,認定された下地構造を採用するなどの配慮が必要である。
カラーアルミサイディングの施工に当たっては,以下の事項に注意が必要である。
・壁面の柱・胴縁については,垂直・水平を確認する。下地作りの代表例を図34に示す。
・各種水切り部材の加工例を,図35に示す。
・水切りや土台回りに接するカラーアルミサイディングの下端部分は,雨水吸水防止のため下端側の芯材を約2cm切る。
・出隅・入隅の加工は,加工部分の裏面の芯材に切り込みを入れ,角材などを使用して表面のアルミ板を折曲げる。出隅加工例を図36に示す。
・横切りや窓回りの細部切込みは,一方向だけ切込みを入れ,切取った部分の裏面芯材を剥がし,残ったアルミ板を折曲げる。
・付属部品(役物)の納まりなどで雨仕舞いの不良箇所は,コーキング材を併用する必要がある。
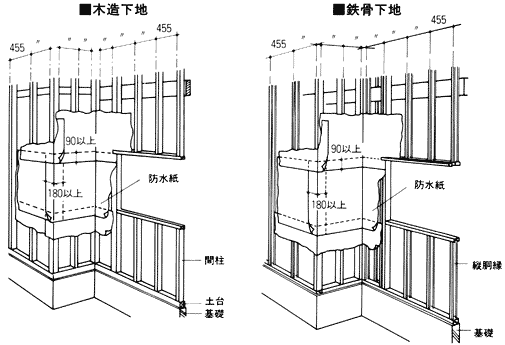
図34 下地の作り方
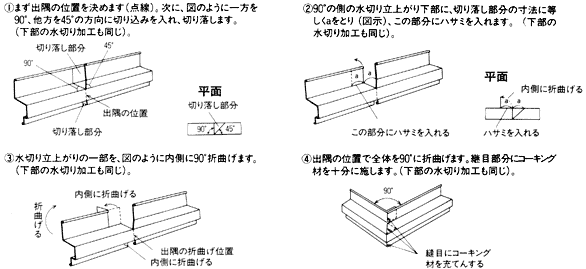
図35 水切り板(部材)隅部の加工例
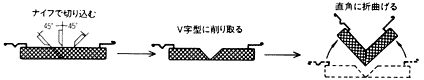
図36 金属サイディングの出隅加工例
3. アルミニウム建材の施工に使用する工具
アルミニウムは比較的切断・折曲げが容易であり,屋根やサイディングなどを施工する場合には,図37に示すような工具が使用される。
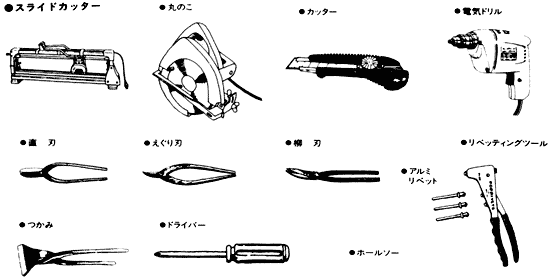
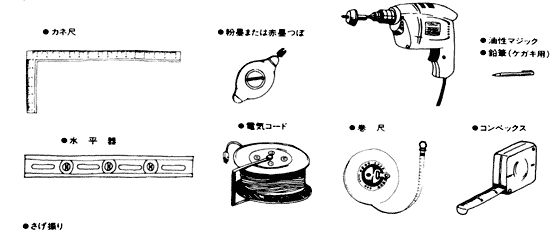
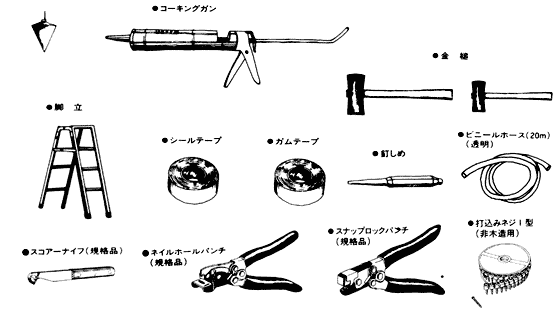
図37 施工工具