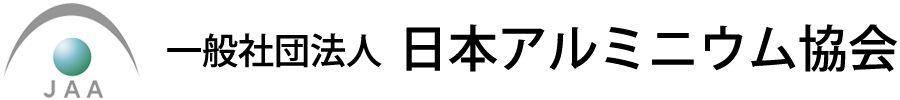過去の官庁関連情報
新着情報
| お問い合わせ |  |  |  |




1 緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域以外の都道府県
緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域以外の都道府県においては、事業者に対して、(略)以下の取組を行うよう働きかけを行うものとする。
・ 在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推進すること。
2 オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策
現在感染が拡大しているオミクロン株については、令和4年2月4日のコロナ分科会提言を踏まえ、政府、地方公共団体及び事業者等は、現行の対策に加え、オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策を強化するものとする。
(略)
5)事業者
・ 緊急事態宣言の発出を待つことなく、業務継続の観点からも、在宅勤務(テレワーク)の活用等による出勤者数の削減目標を前倒しで設定する。






1 緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域以外の都道府県
・ 在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推進。
2 オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策
・ 現在感染が拡大しているオミクロン株については、令和4年2月4日のコロナ分科会提言を踏まえ、政府、地方公共団体及び事業者等は、現行の対策に加え、オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策を強化。
・ 緊急事態宣言の発出を待つことなく、業務継続の観点からも、在宅勤務(テレワーク)の活用等による出勤者数の削減目標を前倒しで設定。
1 まん延防止等重点措置区域である都道府県における取組
・ 人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の削減の取組を推進するとともに、接触機会の低減に向け、職場に出勤する場合でも時差出勤、自転車通勤等を強力に推進。
2 緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域以外の都道府県
・ 在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推進。
3 オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策
・ 現在感染が拡大しているオミクロン株については、令和4年2月4日のコロナ分科会提言を踏まえ、政府、地方公共団体及び事業者等は、現行の対策に加え、オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策を強化。
・ 緊急事態宣言の発出を待つことなく、業務継続の観点からも、在宅勤務(テレワーク)の活用等による出勤者数の削減目標を前倒しで設定。
東日本大震災発生十一年となる3月11日に哀悼の意を表するため、以下を行って頂ければ幸甚です。
①弔旗の掲揚
②3月11日(金)の震災の発生時刻(14:46)に黙とう
1 まん延防止等重点措置区域である都道府県における取組
・ 人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の削減の取組を推進するとともに、接触機会の低減に向け、職場に出勤する場合でも時差出勤、自転車通勤等を強力に推進。
2 緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域以外の都道府県
・ 在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推進。
3 オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策
・ 現在感染が拡大しているオミクロン株については、令和4年2月4日のコロナ分科会提言を踏まえ、政府、地方公共団体及び事業者等は、現行の対策に加え、オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策を強化。
・ 緊急事態宣言の発出を待つことなく、業務継続の観点からも、在宅勤務(テレワーク)の活用等による出勤者数の削減目標を前倒しで設定。

1 まん延防止等重点措置区域である都道府県における取組
・人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の削減の取組を推進するとともに、接触機会の低減に向け、職場に出勤する場合でも時差出勤、自転車通勤等を強力に推進。
2 緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域以外の都道府県における取組
・在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推進。
1 まん延防止等重点措置区域である都道府県における取組
・人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の削減の取組を推進するとともに、
接触機会の低減に向け、職場に出勤する場合でも時差出勤、自転車通勤等を強力に推進。
2 緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域以外の都道府県における取組
・事業者に対して、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推進。
~~経済産業省からのお知らせ~~
現在、経済産業省では、「企業におけるサプライチェーンのサイバーセキュリティ対策に関するアンケート調査」を実施しております。1月6日付けで対象企業のサイバーセキュリティ担当部門(情報システム部、リスク管理部、総務部等)に調査委託先のNTTデータ経営研究所より郵送にてご案内しておりますので、各業界団体様経由でも周知をさせていただきます。
アンケート対象は、業種等を指定した上で無作為に抽出した約1万社となっております。回答期限は1月26日です。
ついては、貴社のサイバーセキュリティ部門に対し、アンケートがお手元に届いている場合はご協力いただけますようご案内をいただけますと幸いです。大変恐縮ですが、アンケートが郵送で届いていない場合、本お知らせはご放念ください。
(調査の背景、目的)
昨今、サイバー攻撃の高度化・巧妙化により、サプライチェーン上の対策が進んでいない取引先の中小企業、グループ子会社、海外拠点等を踏み台とした大企業のネットワークへの侵入や情報漏えいなどが観測されており、取引先企業を含むサプライチェーンのサイバーセキュリティ対策が重要となっております。
こうした背景から、経済産業省は、企業におけるサプライチェーンのサイバーセキュリティ対策を促進するため、企業から取引先等へのセキュリティ対策要請の実態、課題、優良事例等や、サイバー攻撃の被害情報の共有のあり方について調査を実施しており、その一環として、本調査を実施する運びとなりました。
本調査の結果は、経済産業省が企業等におけるサプライチェーンのセキュリティ対策強化に向けた各種施策を企画・立案するための情報として、適切に利用させていただきます。回答結果は、特徴的な事例について個別のヒアリング対象を選定するために利用し、回答した企業・事業者が特定されるような形で公表されることはございません。
以上、お忙しいところ大変恐縮ですが、何卒よろしくお願い申し上げます。
1 まん延防止等重点措置区域である都道府県における取組
・人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の削減の取組を推進するとともに、接触機会の低減に向け、職場に出勤する場合でも時差出勤、自転車通勤等を強力に推進。
2 緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域以外の都道府県における取組
・事業者に対して、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推進。





総務省・経済産業省では、令和3年6月に行う「令和3年経済センサス‐活動調査」を正確かつ円滑に実施するため、調査票の配布に先立ち、支社等を有するすべての企業等の方々を対象に「企業構造の事前確認」を実施します。令和2年10月下旬から順次書類を送付させていただきますので、ご協力をお願いします。






(注)「1回目の調査とは項目が異なりますので,1回目の調査にご回答いただいた希望者の方も,必ずこの2回目の調査にご回答いただくようお願いいたします。」とのことです。

大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が、下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。
大企業等と下請等中小事業者は共存共栄!適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更などはやめましょう!

政府では10月の消費税率引上げに向け、上記のコールセンターを設置し、平日9~17時にご相談を受け付けているところですが、9月・10月については土曜日も
ご相談を受け付けることとなりましたので、ご案内させていただきます。

※政府では、企業の研究開発を支援するため、試験研究を行った場合に法人税額から一定割合を控除する研究開発税制を設けております。平成31年度税制改正において、研究開発税制については、オープンイノベーション型が拡充されるなどの改正が行われました。研究開発税制では、オープンイノベーション活動に関する更なる優遇措置(オープンイノベーション型)が設けられており、共同研究・委託研究にかかる費用の最大30%分の税額控除を受けることが可能です。
※今般発生した熊本県熊本地方を震源とする地震に関連して、工場の操業停止等も見込まれます。
ついては、操業停止や震災の影響に伴って下請企業等に一方的に負担を押しつけることがないよう連絡が来ました。
震災に伴う下請取引等への影響に関しては東日本大震災の際の公正取引委員会のQ&Aをご参考としてくださいとのことです。
公募期間:平成28年2月19日(金)~3月10日(木)12時 経済産業省 通商政策局 国際経済課必着
説明会:平成2月24日(水)10:30~@本館1階東会議室(ミッション) 14:00~@本館1階西会議室(ロビイング)
※ミッションであれば海外展開を考えているアルミ企業を対象に海外へのツアーを組んでみるとか、ロビイングであれば特定の進出国で進出している企業が連携して進出先の政府に働きかけるというような活用が想定されます。

※本事業は、これまでに開発された革新的な技術等を用いて、新たに事業化を行うために民間団体等が実施する実証研究、試作品製造、性能・安全性評価に必要な費用の一部を支援するものです。