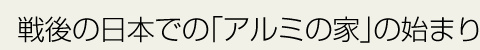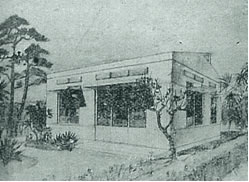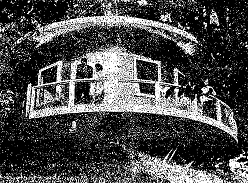戦後のアルミ産業は、48(昭和23)年のアルミ製錬の再開、49(昭和24)年の「重要資材使用制限規則」の解除によって、平和産業として始動しました。46(昭和21)年に設立した軽金属協会の下、50(昭和25)年に、自動車、鉄道車両、船舶部門などとともに、建築用軽金属委員会が組織され、軽金属工事の建築工事標準仕様書原案の作成、軽金属建築ハンドブックの刊行など、アルミの建築部門の普及に努めました。
同時代のアルミハウスへの挑戦としては、星野昌一氏などの指導の下日本建鐵が、47(昭和22)年の軽金属組立家屋試作第1号から、51(昭和26)年の第5号まで製作しました。これらは、薄鋼板の折曲げ材(軽金属の押出し材も検討)あるいは木材を骨組とし、特殊波型のアルミ板を貼った外壁パネルの不燃住宅で、試作に終わりました。星野氏は、戦災での住宅不足420万戸に対して、国内外での木材の確保、熟練した職人の育成に危惧を持ち、都市防火も併せ、「軽量」「堅牢」「正確」な軽金属造による工業力の活用を、訴えました。
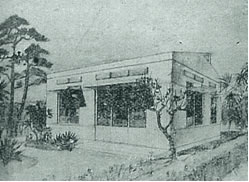
軽金属組立家屋試作
50(昭和25)年の小田原子供文化博覧会には「軽金属製円形理想住宅」が出展されました。金子徳次郎氏が当時海外で普及していた組立住宅の研究を基に設計し、古河電工のアルミ波板65枚(厚0.3、3尺×6尺)、神鋼金属のアルミ平板50枚(0.5、1m×2m)、アルミ総量約150トンを用いて組立てられました。波板は庇裏、外貼り、下見板に、平板は平葺の屋根、ドア、樋などに使用され、波板の外壁は円形でありました。建設費は約25万円で、展示後、革新的な簡易文化住宅として数軒受注しました。
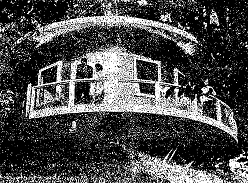
軽金属製円形理想住宅
また、57(昭和32)年の建設省主催「これからの街とすまい展」に、軽金属協会はアルミ業界の協力の下、耐震、不燃架構のアルミモデルハウス(15坪の鉄筋コンクリート造)を製作、展示しました。アルミ瓦棒葺の屋根、アルミ板製の樋、アルミリブ板貼の外壁(一部)、アルミの外廻り建具、アルミエンボシング板の内壁、アルミ吸音板・アルミ箔貼の天井、そしてアルミ箔利用による三層断熱の保温保冷壁など、個人住宅として可能な限りアルミを使用しました。アルミの台所、風呂桶、家庭用日用品とアルミ蒸着の什器備品まで設置されました。


アルミモデルハウス