| ■プレセニリン |
以上がアミロイド前駆体タンパク質遺伝子の話で,二番目の遺伝子はプレセリニンという遺伝子です。それは14番目の染色体にあります。先程のは21番。これはやはり細胞膜を7回から8回貫通する,こういうタンパクです(図15)。アミノ酸が全部で467基。点で描いてあるところに突然変異が世界中で次々と見つかり,すでに40種類以上の変異が証明されています。つまりここが変異してもアルツハイマー病になる,ここで起こってもアルツハイマー病,いろんな場所で起こってもなぜかこのプレセニリンは,アルツハイマー病の発病を非常に促進する。特に先程いいました山形県で見つかったこの遺伝子は30代,28才から29才,30才,非常に早くアルツハイマーを発症させます。世界的にも同じで,こういうふうなのは非常に早く起こる変異の部類として知られています。
このプレセニリンというのもやはり一回ハサミが入りますが,これはこれ自体からはアミロイドは出てこない。先程のはそのものからアミロイドが切り出されましたが,プレセレニンからはアミロイドが作られるのではなくて,どうもアミロイドを切り出すハサミを支える機能をもっている。これが異常になるために,βのハサミがどんどん増えたり,γのハサミが増えたりするのではないかというふうな推定が行われています。いずれにしましても,これは非常に重要な遺伝子で,これのトランスジェニック・マウスもいま作っていますが,これ自体のトランスジェニック・マウスではアミロイドは全然たまっていません。ところが先程のアミロイド前駆体タンパク遺伝子のトランスジェニック・マウスと,このトランスジェニック・マウスをかけあわせると,アミロイド前駆体タンパクのトランスジェニック・マウスでは大体6ヵ月ぐらいからアミロイドが溜りますが,かけあわせると3ヵ月。これがやはりアルツハイマー病の機序を促進する因子として非常に重要であるということが分かってきています。今どこらへんで効いてくるのかは詳しく解析している真最中です。
私たちがやっております研究の一端ですけれども,膜貫通型のプレセニリンというのは小胞体などこういうところに存在していて,そして何らかのタンパクと結合して存在している。そしてその結合のシグナルは,次にまた伝達されて,そしてついにはアミロイドの中でも特に1−42という凝集性の高いアミロイドをどんどん生み出していく,ということなのです。その結果,老人斑に沈着してアルツハイマー病になると(図16)。
もう一つのパスウェイはどうもこちら側つまり神経原線維変化の方です。この神経原線維変化の形成に対しても促進的に働いているということが分かればいいわけです。それからここにアポトーシスと書いてありますが,アポトーシスというのは細胞死のことを云います。Death,つまりこういう異常な遺伝子が発現すると細胞が死んでいく。その機序のひとつは作り出されたβタンパクで,これ自身が神経細胞をやっつけるということがわかっています。ですからこれ自体は細胞毒です。毒物を自分自身で作る。毒だからまずいんで,こうやって埋め込むわけで,それが老人斑なのです。もう一つはこういうふうに神経原線維の変化というものがどんどん起こっていて,脳細胞が正常に機能しない。その結果死んでいく。あるいは他のメカニズムもある。いずれにしても,どうもこの遺伝子は,先程いった三つのアルツハイマー病の特徴すなわち,(1)βタンパクが存在する,老人斑ができる,(2)神経原線維変化ができる,(3)神経細胞死が起こる。この三つの現象を全て説明できつつある,ということで,この遺伝子の機能を解析すれば,やはりその延長線上にはアルツハイマー病の原因解明が存在している,展開しているということなので,多くの研究者が注目しています。次に結合するタンパク質が取れてきますから,とれたタンパク質の機能を解析する,更にその次を解析する,ということで全体のパスウェイが全部解明されるというのは数年のオーダーで分かるようになるということです。
|
|
 |

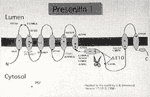
|
| 図15 |
プレセニリンにおけるアルツハイマー病発症の促進因子
|

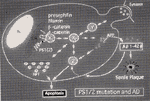
|
| 図16 |
プレセニリンの効果。一つはAβ42の増加,老人斑形成へ,もう一つはアポトーシスへ。
|
|