| ■神経細胞死の要因 |
それから神経細胞はなぜ死ぬのか,一つは先程言ったβタンパクが溜るから,それからもう一つは今のような神経原線維変化が細胞に溜るからだと。その他に,老化自体でも細胞というのは枯れるように死んでいく。虚血でも死ぬ。それから神経栄養因子とか,神経細胞というのは絶えず栄養をもらってないと生きていられないのです。その栄養因子として,ノーベル賞をもらった人が発見した神経成長因子Nerve Growth Factorというのがあります。そういったファクターがわかってきて,今ではもう何十種類というファクターが知られてきております。で,一個ぐらい無くなっても他のものがカバーするので,なかなかこれだけでは死なないのですが。その他,グルタミン酸といったような興奮性のアミノ酸で,細胞が異常に興奮して死んでしまう,というメカニズムもあります。それからストレスによることもあります(図20)。
例えば,虚血によって細胞が死ぬというのは脳こうそくで血液が行かなくなればそれから先は,栄養や酸素がいかないから死ぬわけですけれども,ぎりぎりの状態のところで,境界領域でどういうことがおこるかといいますと,虚血が起こると興奮性のアミノ酸というものがどっとでてくる。そうすると,例えばグルタミン酸の受容体というのに結合すると,なぜかカルシウムがどっと細胞の中に入り込んでくる,そうするとこの細胞は死んでしまうということです。脳梗塞なんかでも,本当に血液が行かないところは死んじゃって仕方がないんだけれども,その周辺で,こういうことがどんどん起こるものですから,なるべくこの脳梗塞の範囲を縮めてやろうという研究があるわけです。そこでこの興奮性のアミノ酸をいかに処理するかという治療薬の研究が進んでおります。アルツハイマー病でも非常に脳血流は落ちてるといわれており,こういうことが実際神経細胞死を起こしている可能性があるということで非常によく研究が進んでいます。こういうものを防ぐ治療薬,予防薬というものも研究中という状況です。
神経栄養因子の枯渇というのは,神経細胞があると神経細胞に肥やしを絶えずあげなくちゃならない。その栄養というのは,一つ前の細胞からだいたい作られていて,その作られた栄養あるいはその周辺の細胞から作られた栄養を取り込んで,取りこんだ栄養が神経細胞に運ばれていって,この神経細胞を元気よくしていく(図21)。ところが年をとって先の方からどんどん死んでいきますと栄養が届かなくなってもとの細胞も連鎖反応的に死んでしまう。ですから,最初にお見せしたのはずいぶん細胞が減っていましたが,あそこ自体には老人斑やβタンパクや神経原線維変化はありませんから,先の細胞のある場所,ここにはものすごくたくさんの老人斑や神経原線維変化があります,この細胞が死んでしまった結果,アセチルコリン産生細胞が二次的にこちらが無くなる,という機序は充分説明できるのです。
それでは,この栄養を実際脳に打ったらどうなるかということで,すでに,サルを使って,先程言った神経成長因子といったものを脳に注射をする,という治療法の研究が進められています。あるいはそういう栄養因子を産生する細胞を移植してやる,ということで脳の老化を防いでやろうという研究も進んでいます。
それから,βタンパクが作られると,なぜ細胞が死ぬのか。ここのところがもう少しわかればということで,その辺のメカニズムの解明も行われております。βタンパクというものが作られると,アミロイドといいましたけれども糖がくっついてくるわけで,糖がどんどんまぶされていく。なぜそんなことが起こるかというと,ミクログリアとかマクロファージといった細胞は,カスのようなものを食べる細胞なのです。実は糖がくっついてくると,スカベンジャーという異物を処理するための受容体があるのですが,その受容体にくっつきやすい。その一つがスカベンジャー受容体とか,あるいはレイジといわれています。この受容体にβタンパクがくっつきますと,それをとり込み,細胞内で異物を処理するわけです。その処理の過程で,細胞内で,NO(一酸化窒素),インターロイキン1という炎症を司る物質,それからTNFαという炎症を司る物質,こういったものがつくられて出てくる。その結果,これらはみんな細胞毒ですから神経細胞が死ぬであろう。実際神経細胞自体にもこういう受容体が発現しているといわれ,これに,βタンパクがくっつくと細胞の中で活性酸素即ち,非常に毒性の高い酸素が作られ,その結果細胞を死亡させることになる。
こういった,ラディカルといいますけれども,活性酸素のようなものを中和するといいますか,取り除く薬がビタミンE,それから炎症をとる薬は抗炎症剤です。そこでリュウマチの患者さんを十万人集めて,アルツハイマー病の頻度を調べたら普通の人たちよりも明らかにアルツハイマー病が少ない。それで,どうもこの抗炎症剤が効いてるんじゃないかという推定で,抗炎症剤を飲んだ人と飲んでない人を調べると,飲んでる人のほうが明らかにアルツハイマー病が少ない。おそらくこういう炎症を防ぐことによって細胞死を防いでるんじゃないか。あるいはビタミンEを非常に大量でありますが,食べるほどですね,患者さんに食べさせるとアルツハイマー病の進行が少し鈍ったという報告なんかあります。βタンパクが出来たとしても,次のステップをある程度和らげることが可能になる,出来るんじゃないかということです。まだまだ不十分ですけれどもこういうことも実際あります。
先ほど炎症といいましたが,アルツハイマー病で炎症なんか起こるわけ無いと思ってらっしゃるかも知れませんけれども,実際にはこのように,これが老人斑,黄色く染まっているのはβタンパクのアミロイドですが,炎症に近い状態になっているのがわかります(図22)。組織に障害がおこって,神経が変性してしまう。障害が起こると,アミロイドというものがまた作られてしまう,傷を修復するために,アミロイドの前駆体タンパクがまたここで作られてしまう。またどんどん作られると,βタンパクというのはまた溜ってくる。ここで悪循環を引き起こしてこのような老人斑ができあがってしまう。そういうものが,最初は一個の粒のような種のようなものだったものから,どんどん大きな立派な老人斑となり,そういうのが脳のあちこちに出来て,その結果脳の細胞が障害を受け,アルツハイマー病というものがどんどんできあがってしまう,ということで老人斑というのは非常に大事で,そこには炎症という現象があるんだということが理解できると思います。
最後に,ストレスがやはり悪いというお話をしたいと思います。神経細胞が死ぬ機序には,今いいました老化とかアミロイドとか原線維変化とかあります。最後にストレスをあげたいと思います。なぜストレスで神経細胞が死ぬかと思われるかもしれませんが,これは実際に,人間でもあるのです。
例えば戦争になって捕虜になった人たちです,捕虜になった人たちを,戦争が終わってずうっとフォローアップしてみますと,ぼけてる人,神経障害を持っている人,うつ病になっている人,いろんな精神神経系の障害を持ってきている。実際,それを動物で再現することが出来ます。これはラット,ネズミです。若いうちはなかなかストレスを加えても平気ですけれども,年取るとなりやすい。それからオスのほうがなりやすい,ということが分かっていました。それで,若いラットを去勢をしまして,精巣を摘除して,すくなくともホルモンの状態からは年をとった状態にしたわけです。そういうラットを,首から下を決して冷たくはない20度の普通の水につけます。こう首から上は出てますから息はできる。それから小さいケージ,この一個のケージではやっと体が一つはいる程度の狭いケージなもんですから,身動きが取れない状況で首から下を水につけてやるとものすごいストレスがかかるのです。泳げないですし,溺れるんじゃないかと。こういうことを一日二十分だけやりまして,後はもう自由にしておきます。また次の日に,同じことをやり,こういうことをずうっとやりますと,こういうことになります(図24)。これがネズミの海馬という,記憶の中枢です。一個一個は神経細胞で,これは正常のラットの海馬できれいな神経細胞が並んでます。これが,今言ったストレス二十分を一過聞かけたらぽつぽつと,なにか黒っぽい細胞が出来ています。二週間やるとほとんどの海馬の細胞が黒くなる。これは五週間なのですけども細胞はもう消えちゃったところもあり,こうなると細胞は生きてはいるんですがほとんどは正常に働いていない。こういう段階の動物で記銘カテストすると非常に落ちる。つまり,性ホルモン,この場合はオスですからテストステロンというホルモンですけれども,テストステロンというホルモンが非常に低い状態でストレスを慢性に加えると神経細胞が死ぬということです。
よく呆けたお年寄りを,暴れるものですから,ベッドにくくりつけるんですが,あれはこの実験やってるのと全く一緒でして,おとなしくなったと思ったら実は神経細胞がみんな死んでる。非常に危険なのです。もうアメリカでは絶対に縛りません,まあ田舎の病院にいけばまだ縛ってますけど,手が足りませんから。なるべく自由に徘徊させる,これがベストなのです。そうするとまあ恐らく少しホルモンを入れたらいいのではないかということで,今女性ホルモンをアルツハイマー病の進行予防に使っている,実際日本でもアメリカでも使っています。これはエストロゲンという女性ホルモンを使うと,やや神経細胞が良くなる,神経細胞が生き生きとするにはやはり性ホルモンが必要らしいということなのです。
|
|
 |

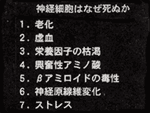
|
| 図20 |
神経細胞死の原因
|

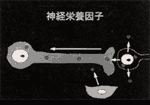
|
| 図21 |
神経栄養因子
|

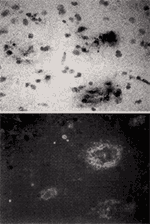
|
| 図22 |
脳内の炎症
|

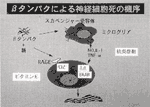
|
| 図23 |
βタンパクによる神経細胞死の機序
|

実験開始時
1週間
3週間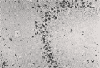
5週間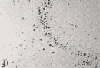
|
| 図24 |
マウスの海馬に生じた
神経細胞死
|
|